⚫︎セラピーとしてのセッションとプロとしての練習
EKOの練習は、基本的には、デイセンターで音楽セラピーとして行われたセッションの延長です。
しかし、デイセンターでのセッションは、「一緒に音楽を楽しむ」ことがメインであり、楽器演奏の上達や、あるいは曲を上手にまとめていくことを狙いとするものではありません。
なので、演奏の上達を目的とする練習とは、性格が違います。
セラピーとしてセッションをしている時は、それぞれのメンバーにこちら側が合わせていこうとする姿勢ですから、セッションの展開はリードするにしても、メンバーのあり方や演奏の仕方について、こちらからいろいろ要求することはありません。
ところが、観客を相手にするとなると、状況が違ってきます。
演奏も自分勝手にするわけにもいかないし、ステージで立つ場所や向きなども含めて、いろいろ形を作り上げていかなければなりません。
つまり、曲の練習をしなければいけなくなり、そうすると、リードする側としてはいろいろ要求することが出てくるわけです。
今まで自由にやってきたものが、練習ということで好きなように出来なくなることは、メンバーとの関係とか「やる気」を考えると、慎重にやらなければなりません。
「音楽は楽しいもの」と感じている部分は、何よりも大事にしなければいけないのです。
そこで、セッションから練習への姿勢の転換は、形としてはセッションと同じように続ける中で、「観客の前で演奏する」ことを練習するという、違う性質のものを同時に進める方法で行いました。
つまり、今まで通りのセッションのように、曲は途中で止めることなく演奏をして、指示をする場合は、リーダーである僕が今までのように主導権を取り、何かの変化を求める場合には、「悪いものを直すのではなく、良いものを伸ばす」姿勢で、セッションの手法を使っていく方法です。
そのため、何か指示する場合には、「ほら、今演奏してるから、誰かが見てるよ」などと、人前で演奏することが自分のやり方を変えるモチベーションになるように促して行きました。
そしてまた、発表会でお披露目するように「お行儀良く」ということではなく、メンバーひとりひとりの個性が自然な形で出るように、その人のありのままの姿は大事にして、曲の出来というものや行動に対しては、その場で臨機応変に対応出来る方向で練習を行っていきました。

「おすすめグッズ」
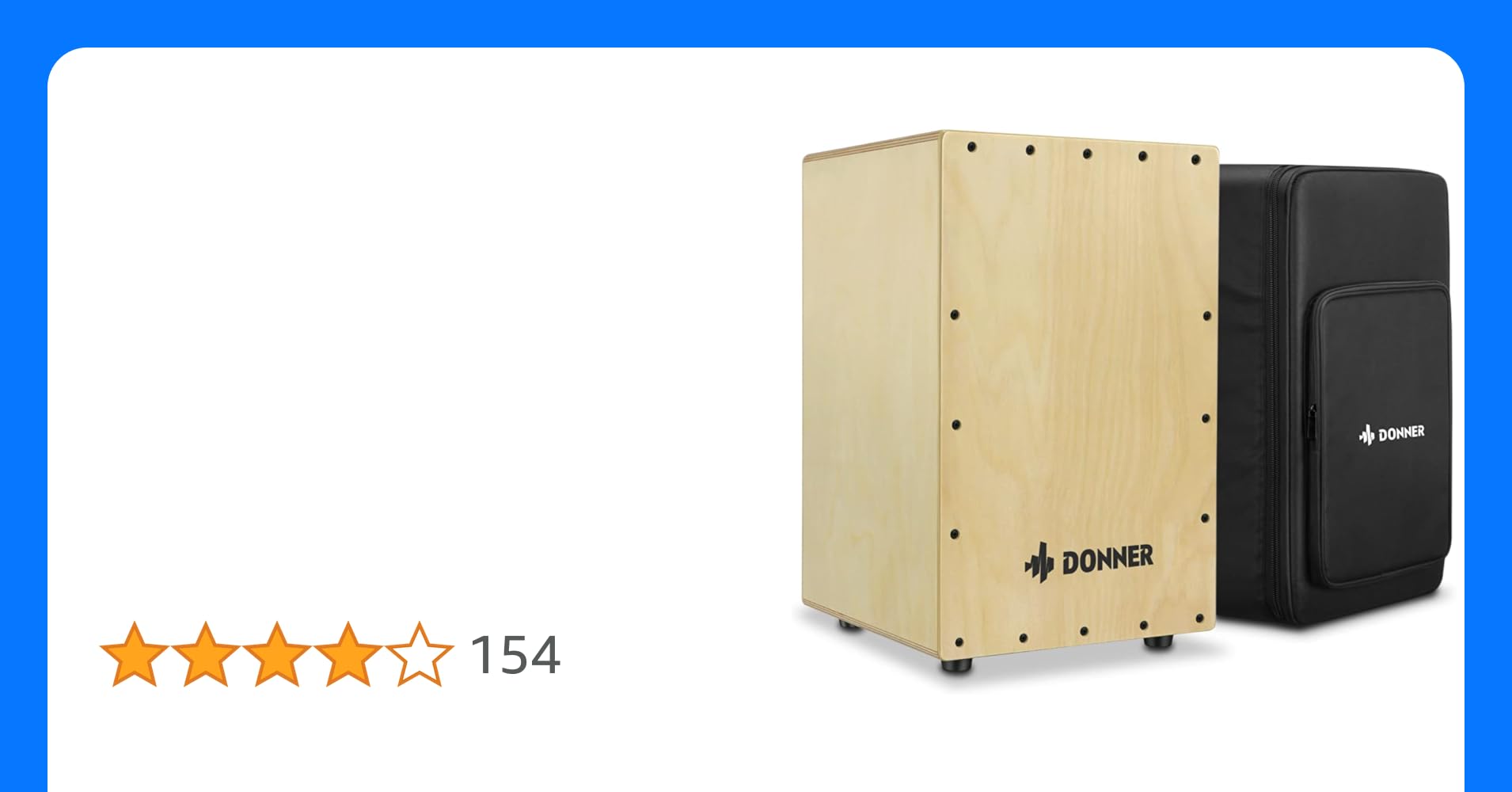
ボッセは、元々エクトルプ・デイセンターの利用者ではなく、他のデイセンターに通っていました。
彼とは市内の余暇のサークルで一緒だったのですが、そのリズム感は抜群でした。
しかし、僕がその後そのサークルを止めてからは音楽をする場がなくなったというので、EKOの練習や演奏の時には参加出来るようにいろいろ調整をして、やがて正式のメンバーになりました。
彼のリズム感は素晴らしく、トムトムを担当するとすぐそれに没頭するようになりましたが、とにかく、その音は他の音を消してしまうほど強かったのです。
隣にいるメンバーは自分の音が聞こえなくなるので、ボッセに食ってかかることもありました。
観客の前では、そんな光景はできるだけ避けたいものです。
そこで、練習でボッセのトムトムの音が強すぎる時には、メンバー全員に「ボッセの音、凄いね。みんなボッセのように音を強く出してみようか」などと言って、全員で耳が割れるような音を出すようにしました。
ボッセは褒められたと思ったらしく、ますます強く叩くし、他のメンバーは「負けるか!」という表情で、ボッセの音よりも強く楽器を鳴らそうと、それはまた凄い音になりました。
一通りそれが終わると、「今のは、凄かった。流石だな〜。じゃあ、今度は反対の小さい音は出せるかな?」と言いながらボッセを見ると、案の定、「そんなこと、出来ないわけがない」という顔をして頷きました。
「じゃあ、やってみよう!」と言って僕がギターを聞こえないほどの小さい音で弾き始めると、ボッセもみんなも、今度は負けないように、思い切り小さな音を出しました。
そして、ボッセに向かって手のひらを下に向けて上げ下げしながら、「いいぞ、ボッセ。もっと小さく…、そうだ…!」などと言いながら、ボッセが頷くのを待ちました。
ボッセは僕を見ながら、ほとんど聞こえないほどの音を出しました。
ボッセが僕の手のサインの意味を理解すると、後はそれほど問題がありません。
彼がトムトムを強く叩きすぎると、僕はボッセにそのサインをするだけで、トムトムの音が弱くなるようになりましたし、「ここでソロが欲しい」という時には、その手を挙げるとボッセもそれに連れて音を強くするなど、コントロール出来るようになったわけです。
もし、それをやらずにみんなの前で「音が大きすぎるから、小さく叩いて」などとボッセに指示をしたら、繊細すぎるほどの彼は、きっと萎縮して打ちのめされていたことでしょう。
「おすすめグッズ」
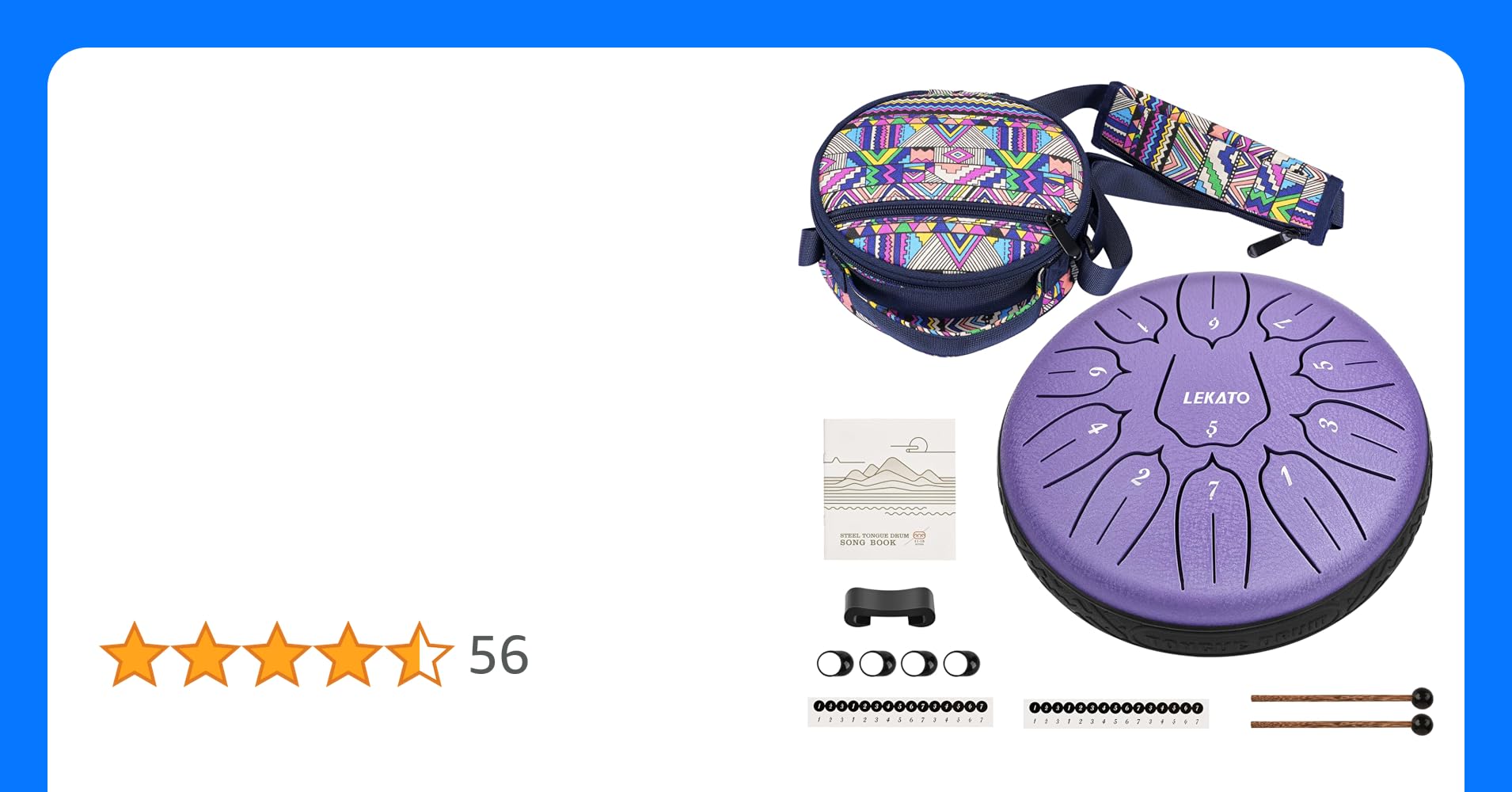
⚫︎全体練習と部分練習
音楽セッションにあったグループ・ダイナミックスは、EKOが練習を続けていく上で大切なものでした。
そこでは「間違い」というものはなく、それぞれが何をやってもグループの中に溶け込むことができ何でも許されるからこそ、自分を思う存分発揮できる場にもなり得ました。
しかし、バンドとなってからの練習が多くなると、やりたいことばかりではなくなるし、自分のやり方を周りに合わせなければならないことも増えてきます。
また、そればかりが続くと、実際の演奏の場で思い思いの表現が出難くなってしまいます。
EKOが観客を前にして演奏する時は、メンバーたちが、一緒に演奏しているリーダーたちが驚くほどの、自発的でしかも自然なパフォーマンスを演じるというのがEKOの持ち味です。
そのため、練習を全体練習と部分練習という二つのやり方に分けて行うようにしました。

全体練習とは、全員が稽古場のステージに立って演奏を通して行い、部分練習は、その時の状況によって、一人ずつあるいは数人で、歌の部分や演奏の部分、時には動作などの練習を行うということです。
部分練習では、「この方がより良い」と思われることを何回も繰り返すことがありましたが、全体練習では、セッションの時のようにそれぞれの自発的な動きに任せ、同時にリーダーたちも、メンバーそれぞれの癖や行動に即興的に対応出来るように、実際の舞台のように進行していきました。
メンバーの、ペーテルの例を話したいと思います。
彼は、作業も積極的に行い、みんなが嫌がるような重い機材を自ら進んで運ぶなど、活動には非常に真面目な姿勢を持っていました。
舞台ではカバサという打楽器を担当し、頃合いを見計らっては舞台の前方に進んで、観客を引き込むこともよくありました。
ダンスも好きで、リズム感も決して悪くはなかったし、速いテンポの曲では、何も問題はありませんでした。
ところが、ブルースやバラードの緩いテンポの曲になると、テンポを落とすことをせずに、むしろロックなどのテンポよりも、もっと速く弾きだすのです。
どうも、彼のリズム感の問題ではなく、遅いテンポになると自分の動きがコントロール出来なくなって、それがまた不安に感じられて余計にテンポが速くなるようでした。
一度、海外公演でホテルに泊まった時に彼の隣の部屋にいたのですが、その時彼が部屋の中で大声を出して歌っているのが聞こえました。
ラジオから流れるバラードの曲を、正確な音程とリズムで歌っていたのです。
一人でいる時は全く不安がないのですが、グループで練習をしたり観客がいる時には、見られている自分を感じて不安になるに違いありません。
「おすすめグッズ」
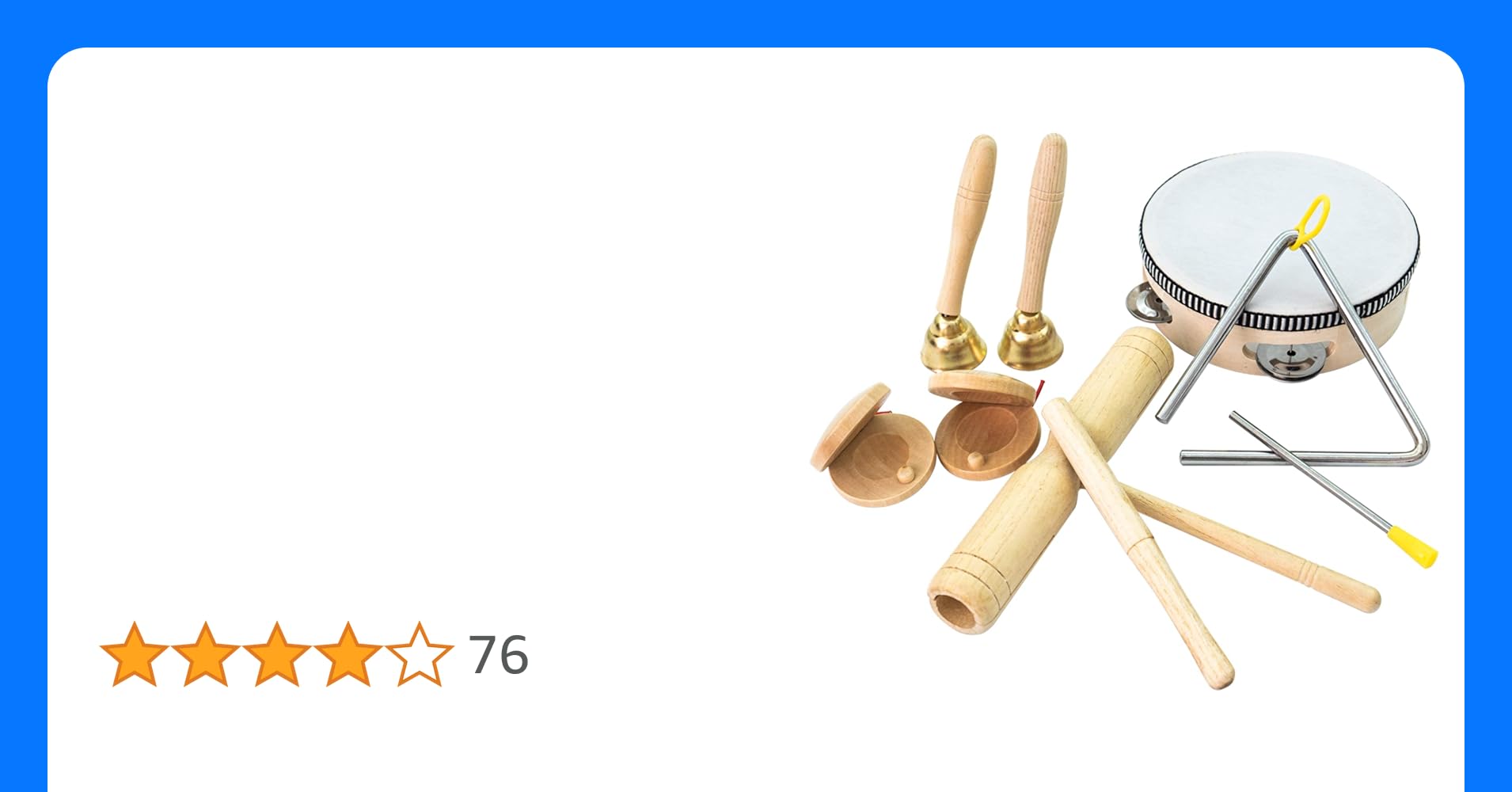

そこで、デイセンターに戻ってから彼を部分練習に誘い、彼とダンスをすることにして、練習とは言わずに「今日は何もないから、音楽でも聞いて踊ろうか?」と誘いました。
スタジオ担当で、またEKOではドラムを受け持っている音楽リーダーのニクラスに頼んで、速いテンポの曲とゆっくりしたブルースを選んでテープで流してもらい、ペーテルには「いい曲だね〜」と言いながら自分で踊り始めました。
もしかしたら、何かあるのではないかと思っていたに違いないペーテルは、最初は疑わしそうに僕を見ていましたが、そのうちに身体が動いてきました。
音楽がかかると黙っていられなくなるのは、EKOのメンバー全員に共通しているところです。
時間が経っても、僕が練習らしきことは何も言わずに、世間話のようなことを喋りながらただ踊っているので、彼もだんだん安心したようです。
その様子が分かっても、僕は何も言わず、わざと見ぬ振りをして踊りを続けました。
そのうちにゆっくりしたバラードの曲になったので踊りながら彼の様子を見ると、彼も同じテンポで踊っているのが見えました。
動きのテンポは、そのバラードとピッタリと合っていたのです。
それ以来、ステージで何かの理由で彼のテンポが速くなると、僕は演奏をしながら彼と踊るようにしました。
テンポが合う日の彼は機嫌が良くて、ロックのナンバーになるとステージの前方に出て、パフォーマンスを実に堂々とやるのです。
⚫︎曲作り
EKOが演奏する曲は、すべてオリジナル曲です。
もちろん、音楽セッションをしていた頃はセラピー的な曲を使っていましたし、グループを結成した頃は自分たちの出来る曲を演奏したりしたこともありましたが、バンド活動を開始してからは努めてオリジナルの曲だけを演奏するようにしました。
障害を持つ人がステージで何か既成の音楽を演奏すると、往々にして、「上手くできた」とか「間違わずにやっている」という評価をされることがあります。
中には、「障害を持っている割に、上手だ」という人もいます。
僕らは、それが嫌でした。
僕らは、ステージで障害というものを披露しているわけではないのです。
それぞれ違う条件は持っているとしても、舞台の上ではそれぞれが自分の個性を、思い切り表現しているわけです。
ステージの上では、サポートの音楽リーダーも含めて、全員がバンドのメンバーであり、お互いの出来ることを、それぞれ100%出し合っているわけです。
そこには、障害という壁があってはいけません。

「おすすめグッズ」
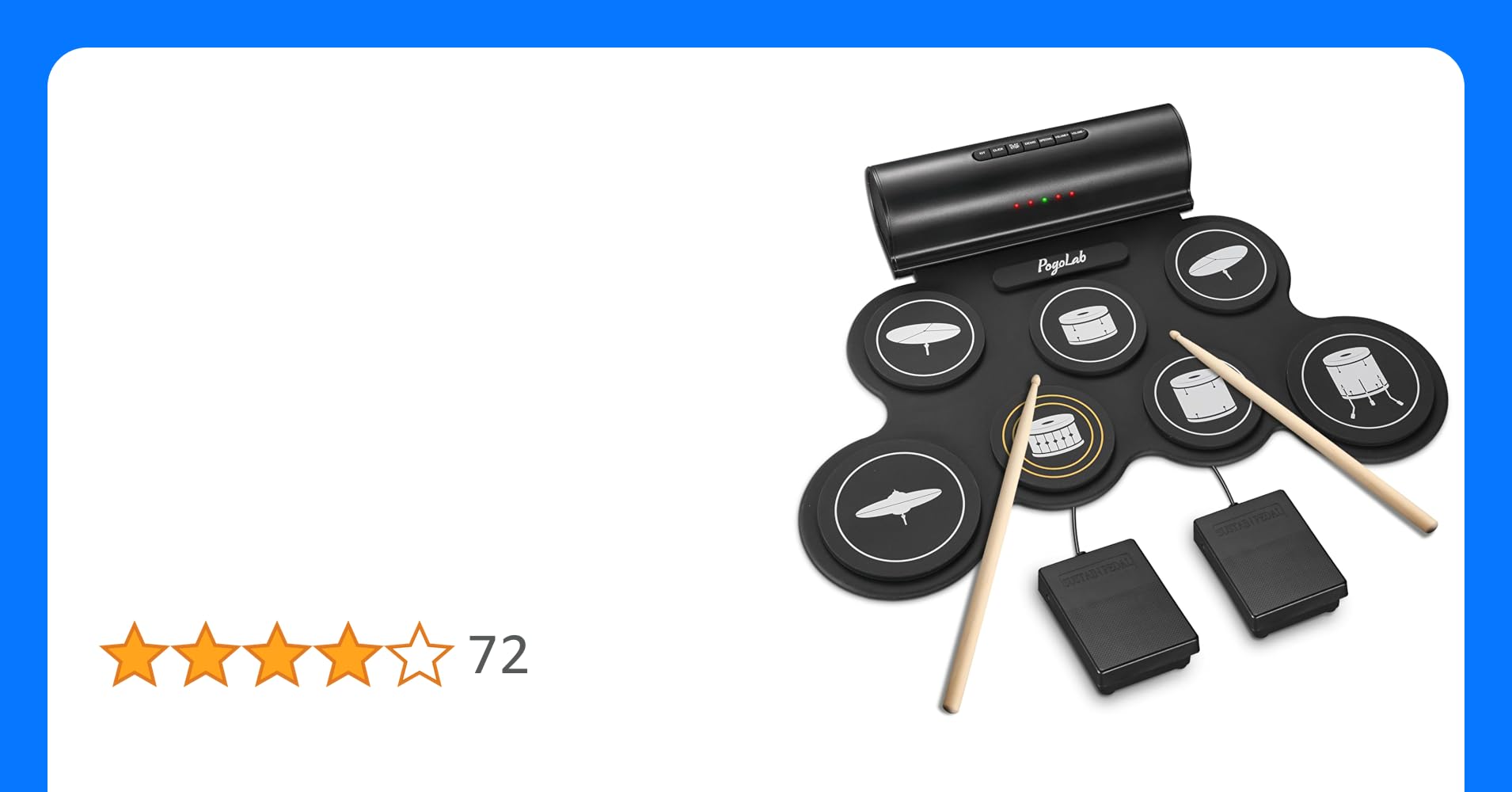
既成の曲を演奏すると、聞いている人はすでに曲の展開を知っている場合が多いので、観客の目はどうしても障害のある人に集まってしまいます。
またリーダーという立場にいる人は、なるべく目立たないように控えめになってしまいがちで、結局は障害というものを見せることになってしまいます。
ところが、それがオリジナルの曲であれば、観客の目もグループ全体に集まることになるし、何をどうやろうと、僕ら自身の姿を見せていることになります。
「自分たちのオリジナルを見せる」というのが僕らのポリシーでした。
オリジナルの曲を作るにあたっては、最初の頃はやはり音楽セッションの時のように、僕が作って練習の中で取り上げることが多くありました。
セッションでの音楽の展開はリーダーである僕が勧めてきたので、そうすることが自然だったこともあります。
しかし、活動を勧めていくうちに、他のリーダーたちの中にも曲を作る人が出てきて、それも同じようにレパートリーとなっていきました。
EKOのバンドメンバーは、結成の頃から多少の入れ替わりがあって、バンドの形が定まってきた頃には、利用者であるメンバーが12人、職員や学習連盟所属の音楽リーダーが、僕を含めて4人、この他にサポートの職員が3名いて、総勢19人がEKOのメンバーでした。
音楽リーダーやサポートの職員は「スタッフ」と呼ばれていました。
他の音楽のリーダーが作る曲は、作る人の音楽的なバックグラウンドも違うので、スタイルはロック音楽といってもそれぞれ個性があり、レパートリーに幅が出るようになっていきました。
僕が曲を作る場合には、曲の構成はすべて分かっているので問題はないし、リーダーたちも即座にフォローするテクニックを持っているので、全体練習で即興的に取り上げてもセッションのようにスムーズにいきました。
しかし、他のリーダーが作る場合は、複数でいろいろ話し合いながら作っていく場合が多かったので、そのような場合は、最初から全体練習で取り上げることはしないで、部分練習の際などにリーダーだけが集まって曲をまとめていくようにしました。
全体練習の場では、議論をしたり曲作りのために同じことを繰り返すことを、出来るだけ避けるようにしたわけです。
「おすすめグッズ」

障害を持つ人がメンバーのグループで、オリジナルをレパートリーにするということなら、当然メンバー自身の曲ということも考えなければいけないでしょう。
実際、EKOのレパートリーの中には、メンバーたちが取り上げた題材を曲にしたものがいくつもあります。
でも、メンバーが作らなければいけない、ということにこだわったわけではありません。
もちろん、メンバーがメロディーや曲全体を構成していくことは難しかったわけですが、それは障害というものによるのではなく、ちょうど、音楽リーダーの誰もが曲を作ったわけではないのと同じです。
全体練習の時の練習の合間や、作業やツアーの時など、メンバーたちと話をする中から面白そうな題材、なるほどと思うエピソードなどをピックアップして、彼らの言葉や考えが生かされるようにしていきました。
そして、それをまずリーダーたちで曲のイメージを作っていき、部分練習もリーダーだけでやった上で、全体練習の時に全体で演奏してみんなの反応を確かめていきました。
初めからみんなで創り上げるということをしなかったのは、やはり全体練習の時のエネルギーを大事にしたからです。
⚫︎ブルースとハーモニカ
EKOのレパートリーの中では、ブルースを基調にするロックや、ブルースの曲がいくつもあります。
総勢19人のメンバーということは音楽の好みもそれぞれだし、また音楽リーダーのバックグラウンドも違えば年代も違うのですが、みんなに共通しているのはロックであり、またブルースでした。
流行のポップ音楽やディスコ音楽は別にしても、本来ロック音楽やロックン・ロールはやはりブルースが根底にあります。
そして、ブルースといえばハーモニカです。
メンバーのニッセは、歌詞を覚えるのが早いし、スウェーデンの民謡や歌謡曲でみんなが知っている曲はほとんど歌詞を見ないで歌えるくらいなので、もちろんメインの歌手です。
彼と並んでステージの前方には、アン、グン、スッシー、ネッタンがいて歌ったりタンバリンを叩きますが、ブルースの曲になると、ニッセの歌の合間にみんなでハーモニカを吹きました。
よくある、ブルースのパターンです。
録音した音を聞くとよく分かるのですが、そのハーモニカは、実にブルースなのです。
誰かが吹くゆっくりとしたメロディーも聞こえるし、また誰かの深い低音で刻まれるリズムも聞こえます。
そして、ブルース特有の余韻を残して、ニッセの歌やギター演奏に繋がっていきます。
でも、そんなことはどうでも良いことでした。
第一、ハーモニカの吹き方は一度も教えたことがないし、練習もしたことがなかったからです。

ブルースというのは、大概三つのコード進行というのが普通ですが、例えばC調のブルースだと、コード進行はC・F・Gの三つです。
その場合に、F調のハーモニカを吹くと、それがブルースの伴奏であれば、一つのトーンを吹いたり吸ったり、あるいはどういう風に吹こうが、それはブルースにしか聞こえません。
ブルースの調べになっている伴奏の中では、たった一つのトーンだけ出したとしても、ブルースになってしまいます。
つまり、どういう風に吹こうが立派にブルースになるので、あえてハーモニカの吹き方を教えるとか指示する必要はないわけです。
おまけに、音符をなぞったり、間違わないように気をつけながら吹いているよりも、何倍もブルースなのです。
もちろん、吹く方でももっといろいろやってみたいと思えば、より「カッコよく」なるようにアドバイスはできますが、この場合、本人がブルースを吹いていると実感することの方がより大事です。
ブルースの曲が終わった後の彼らの表情からは、いつも満足している余韻が伝わってきていました。
「おすすめグッズ」
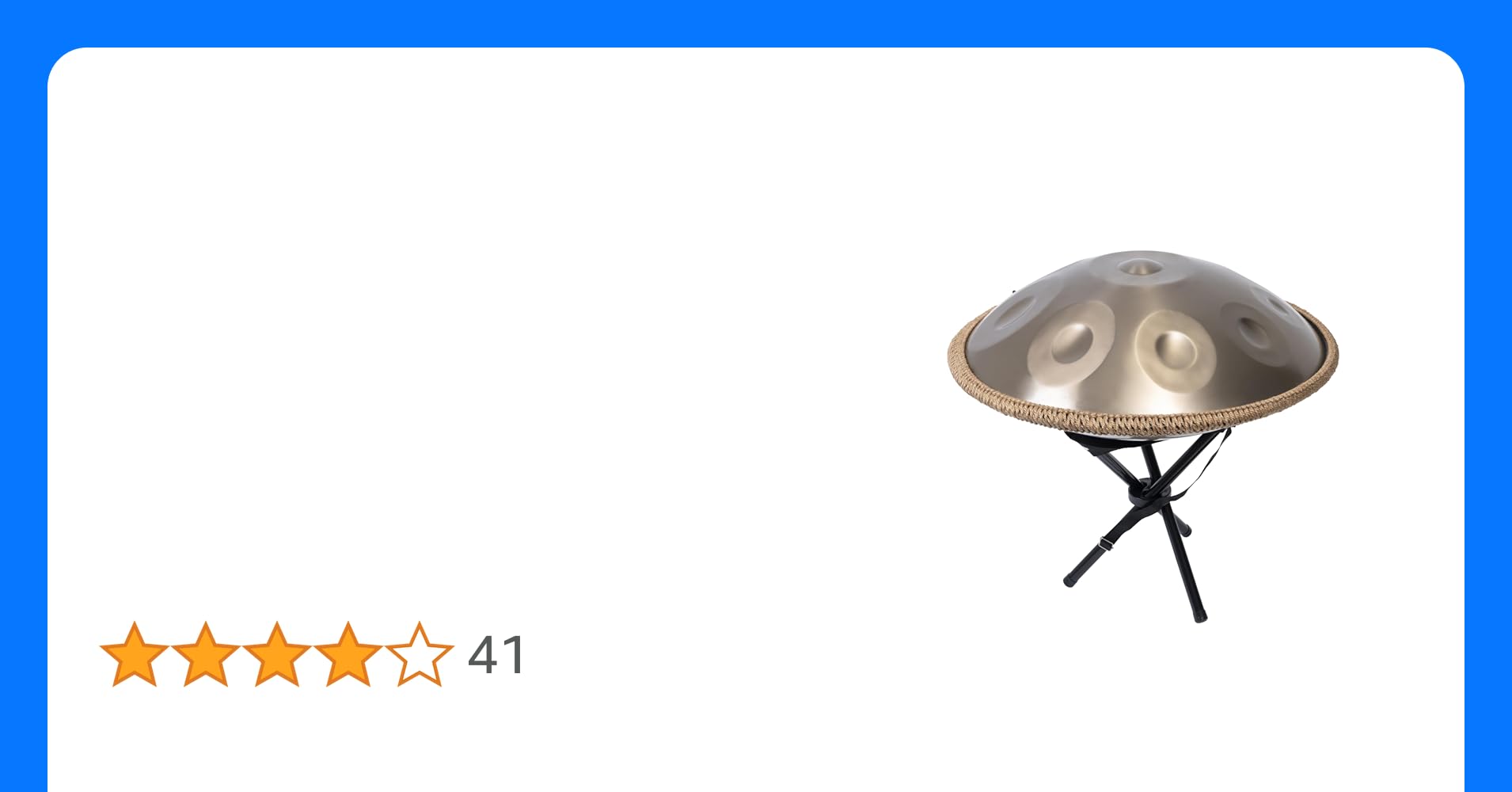
![]()



