⚫︎デイセンター回り
EKOが初めて人前で演奏したのは、前にも述べたように、職員会議の後でのデイセンターでしたが、デビューというものでもなく、どちらかというとグループのまとまった演奏を披露するというものでした。
その後、その時の演奏を聴いたメンバーの親たちが開いた、地区の知的障害者の会(FUB)の忘年会にゲストとして出演しましたが、それもデビューとは言い難く、仲間内に披露するといった感じのものでした。
もちろん、人前で演奏するというのが目標なので、とりあえず市内のデイセンターなどを訪問して演奏することからスタートしました。
器材を運び、ステージと称される場所、多くは食堂や理学療法室のような少しばかり広い場所で器材を仕込むのですが、メンバーたちは何をしていいものか分からず、その場で立ちすくんでいる者も多かったです。
リーダーたちは、仕込みについて何か指図をしようと思っても、時間が迫ってくると、指図するよりも自分たちでやった方が早いとばかりに、汗だくになって仕込みをしたものです。
その間サポート職員は、メンバーたちが仕込みの邪魔になったり、あるいは手持ちぶさたでウロウロすることのないように、彼らの精神的なサポートに専念していました。
しかし、演奏が始まるとそんな雑多な動きもひとつにまとまり、それまで様子を遠目に見ていたデイセンターの利用者たちもステージの前に集まってきて、即席の演奏の場に一体感が広がっていきました。
そして、次第にエクトルプ・デイセンター自体について、音楽活動を積極的に取り入れているデイセンターという評判が立つようになってきました。
そんな状況が一変したのは、グループが結成されてからちょうど一年後に開かれた、コンサートホールでの音楽祭を境にしてからです。

「おすすめグッズ」
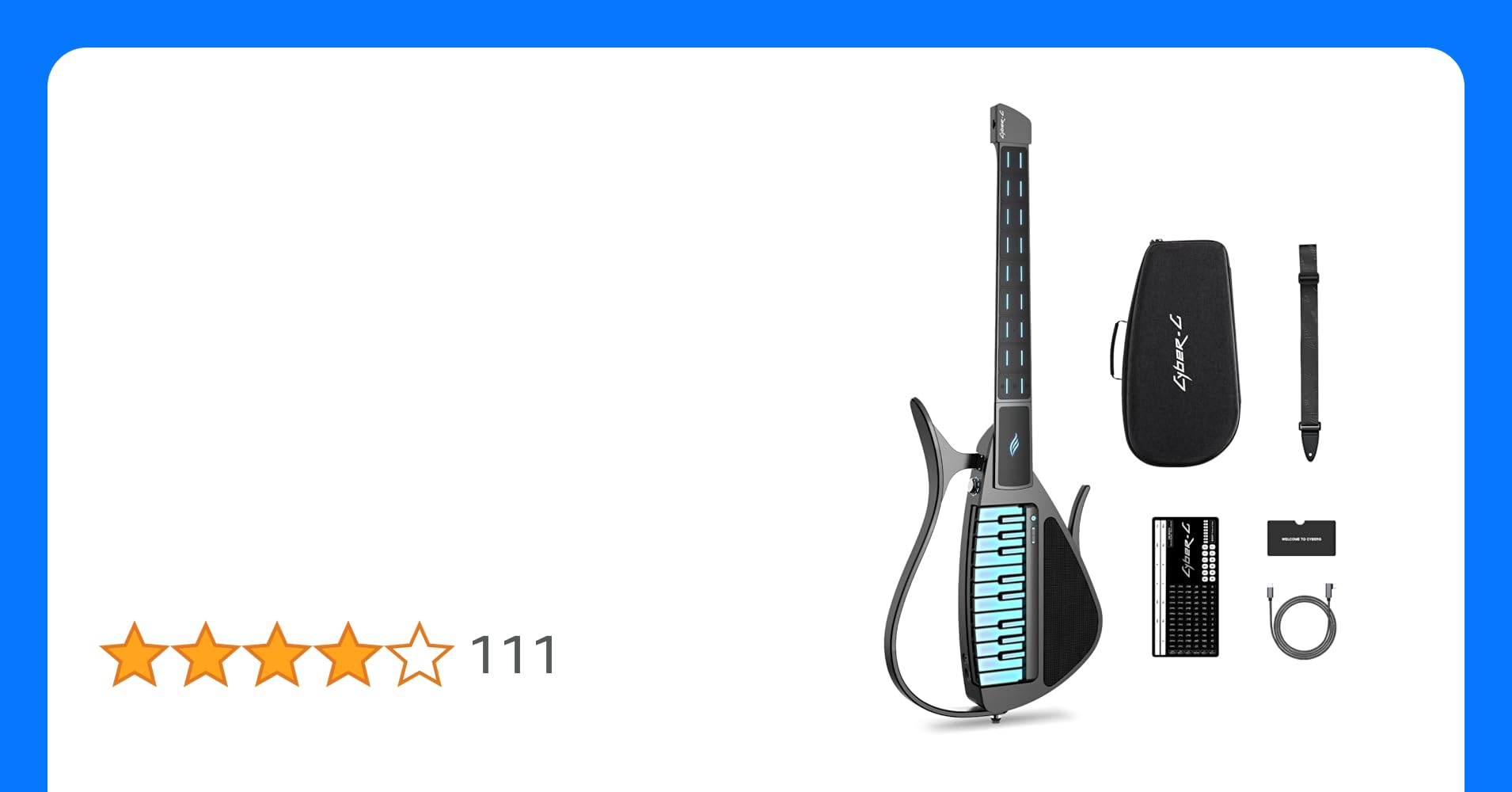
⚫︎「音楽の祭典」を開こう
1987年の春、ある職員会議のあった日に、所長が突拍子もないと思われる提案をしました。
ノーベル賞の授賞式で世界中に知られるストックホルム市のコンサートホールで、デイセンターによる演奏会を開こうというのです。
職員の間には、「えっ!」という驚きの反応が広がりました。
コンサートホールといえば、ストックホルムだけではなくスウェーデンを代表する音楽演奏のメッカです。
いくら「EKOグルッペン」の評判が市内のデイセンターで良かったとしても、いきなりそこで演奏会を開くほどの力はまだない、と誰もが考えました。
実際、バンドのリーダーである僕自身、そこまでの考えは及びもつきませんでした。
しかし…です。
考えてみれば、コンサートホールで知的な障害を持つメンバーたちが演奏をするというのは、正に画期的なことではあります。
折しも、その頃は「新援護法」という知的障害者の新しい権利法が出来たばかりで、障害者の存在を示し、そこで思い切り表現するということは、市内の障害者や関係者にとっても、その意義は想像以上に大きいかもしれません。
所長の意見では、「EKOグルッペン」の演奏の他にも、デイセンターで行なっているセッションをステージで行えば、デイセンターの音楽タイムとして立派にコンサートになる、というものでしたが、それに関しては、僕は丁寧にお断りしました。
デイセンターでのセッションは、基本的に音楽セラピーとして行なっているものです。
セラピーというものは、対象になる人のために行われるもので、人に見せるものではありません。
セッションに適した場所で、一つ一つの音楽を参加している人一人一人の状況に合わせ、セラピストである僕と参加者の間で進められるものです。
また、職業的な専門職ならともかく、外部の人がそれを見て色々評価したり、ましてや楽しんだりするものではありません。
しかし、そのセッションによって、EKOグルッペンは観客を相手に演奏するグループに成長していったことも事実です。
その音楽の力や、音楽によって引き起こされる共感を伝えたり、出演する者も観客も、全員で音楽の歓びを共有することは可能かもしれません。
そこで僕は、デイセンター全員が出演して音楽の歓びを表現し、音楽というものへの賛美と感謝の意味を込めた「音楽の祭典」というテーマで、音楽をEKOグルッペンが演奏するというコンサートを提案しました。
デイセンターでの音楽活動のエネルギーを共有していた職員の多くは賛成しましたが、その趣旨はともかく、前代未聞のコンサートを行うということへの不安を持つ職員もかなりいたことも事実です。
多数決により実施することに決まったのですが、デイセンターはそれから数ヶ月の間、文字通りテンヤワンヤの状況を迎えることになりました。
「おすすめグッズ」
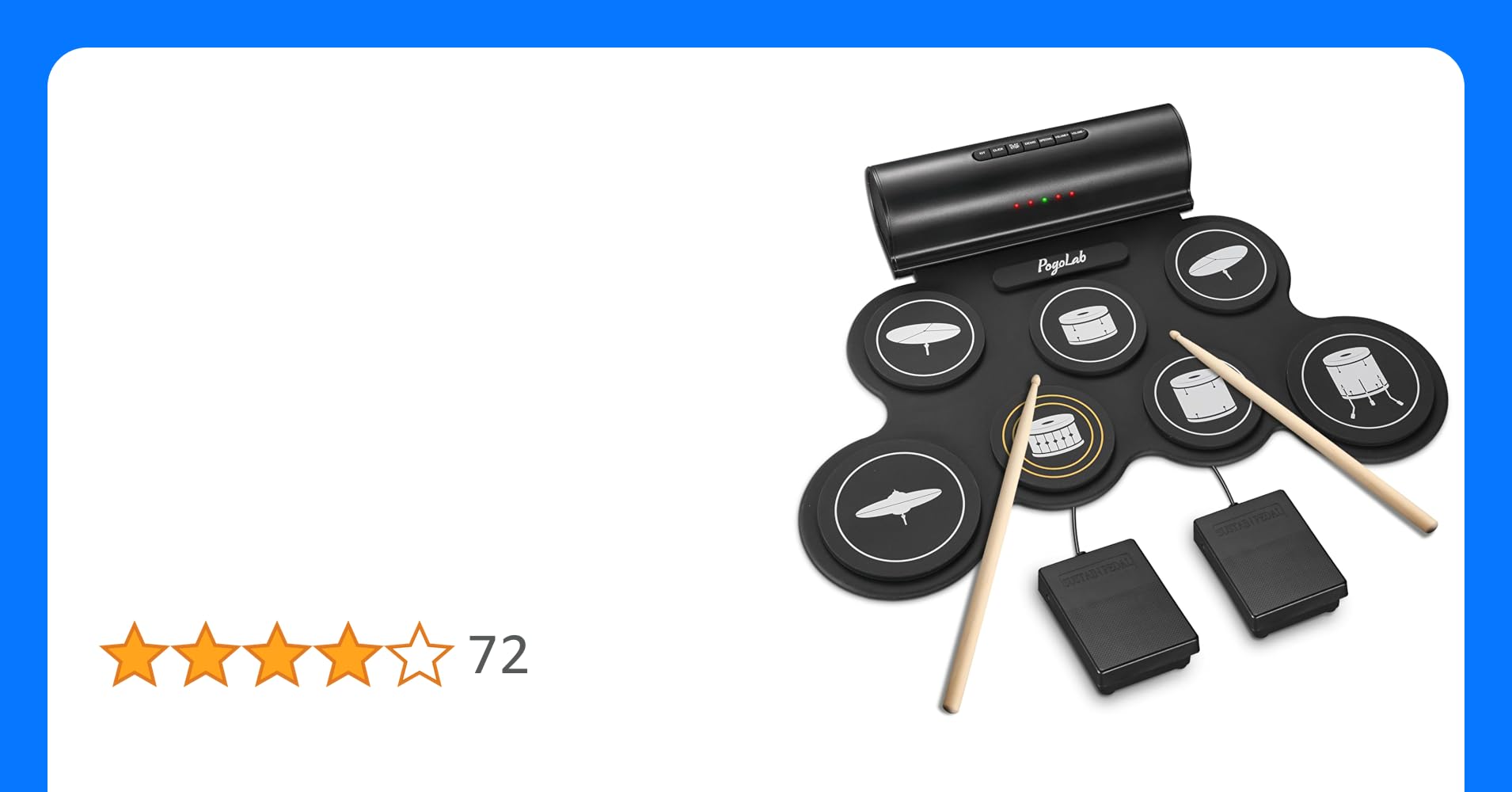

「音楽の祭典」というからには、デイセンターの障害を持つ利用者だけに照明を当てるのは意味がありません。
文字通り全員が出演するということで、誰が障害者で誰が職員かも区別がつかないように、全員が化粧をして衣装も色とりどりのもので着飾ることにしました。
舞台の背景や小道具に至るまで、全部デイセンターで作製することにして、その合間にそれぞれのパートに別れて練習を行い、また公演が近づくと、近所にある公民館を借りて総合練習も行いました。
一方デイセンター側では、工夫を凝らして作ったチラシなどを、市内のデイセンターや学校、福祉担当の役所、あるいは障害者団体や文化団体などに配り、考えられる全てのところへ広報を行いました。
また、地域の新聞にも練習風景の写真で紹介もされました。
何しろ、コンサートを予約する時点で、数十万円の会場費はデイセンターの費用ですでに支払いを済ませているのです。
入場者が少なくお金が戻ってこなければ、所長の首も確実に飛んでしまいます。そのために、1800の観客席の、少なくとも四分の三を埋めなくてはなりませんでした。
所長以下みんな真剣でしたが、とにかく蓋を開けて見なければわからない。
考えてみれば、随分と大きな賭けをしたものです。
⚫︎「音は、何でも音楽になる」
1987年11月6日の木曜日、その日の午後7時半から始まる公演に向けて、デイセンターから全員がそれぞれの思いを抱いてコンサートホールに出発しました。
EKOグルッペンのメンバーは、全員が舞台の仕込みを行うために、午前中には会場に入り、いろいろ準備を行いました。
リハーサルは行わないと、前から決めていました。
プログラムは決まっていて、本番に似た状況での練習はすでに何回か行なっていましたし、また舞台では、総勢75名の出演ともなると、一つ一つの行動を細かく決めていたとしても、予期しない動きが出てくるものです。
大事なことは、舞台でどのような状況になっても、周りの職員たちが適切なサポートができるということです。
そのために、それぞれ即興的な対応が出来るように練習も進めてきました。
リハーサルの際に、照明や暗い観客席を感じることで、より緊張感が高まるかもしれません。
それよりも、本番では新鮮な感覚で舞台に上がる方が、演じる方にも観る方にも生々しい共感が生まれるだろう、と確信していました。
「おすすめグッズ」
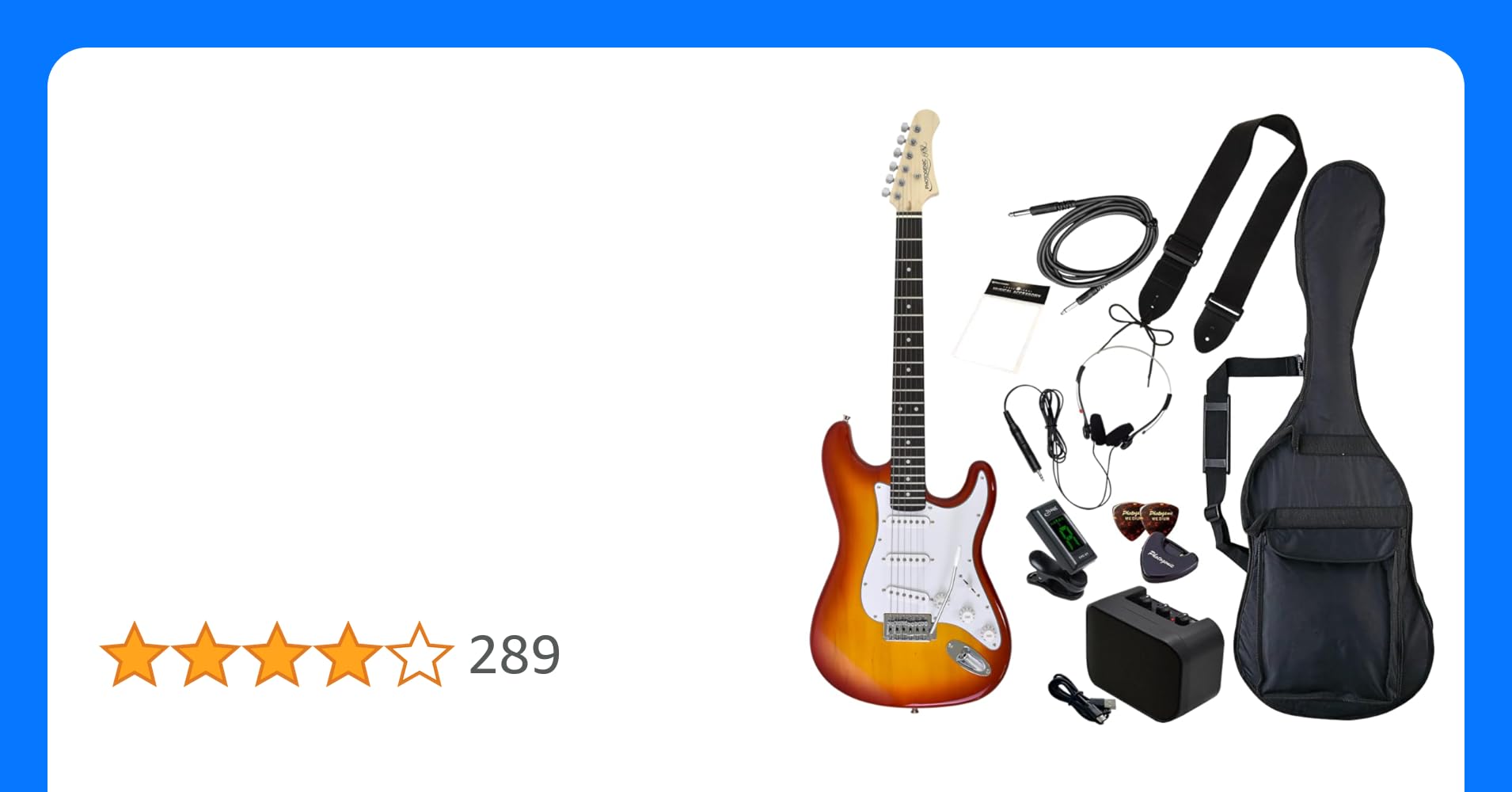

予定時刻になると、続々人がやってきました。
舞台のすぐ近くに用意した車椅子の場所は、開場とともにすぐに埋まってしまいました。
客席は明るい照明にしてあったので、舞台の袖で見ていると、観客が次々と席に着くのが見えましたが、開演が迫る頃には二階も含めた会場が人でビッシリと埋められました。
満席の観客が、一体何が始まるのかと期待感に胸を膨らませながら舞台を見つめていました。
そんな中で、どこからか鐘の音が聞こえ出し、それがいくつもの輪になって会場に広がり、その音が大きくなるにつれて照明がだんだん暗くなり、やがて舞台も観客席も真っ暗になりました。
暗闇の中で鐘の音がだんだん小さくなって消えそうになると、舞台に突然スポットライトがあたり、そこにはピエロの格好をした女性が二人立っていました。
ピエロの一人は耳に手を当てて、何かを聞いている様子。
もう一人がそれを見て、
「何をしてるの?」と尋ねます。
「音楽を聴いてるの」と、聞かれたピエロが答えます。
「ああ、さっきの音?でも、あれはただの音じゃない…」と言うと、
「そうだよ。でも、音が音楽になるのさ」との答えに、もう一人は、
「音楽になるの?」と、また聞き返します。
「そうだよ。聞きたい?ほら、聞こえてくるよ…聞いてごらん、音楽だよ」と答えると、二人とも音のする舞台の袖の方を見つめます。
やがて、袖の方から出演者全員が「音は、何でも音楽になる」という、デイセンターのセッションで普段歌っている曲を歌いながら舞台に出てきました。
それと同時に舞台の照明が次第に明るくなりました。
EKOグルッペンのメンバーは、舞台の奥にあるセットに向かい、楽器を手にすると演奏を始めながら歌い続けました。
そして全員が舞台に出て、「音を出そう、音楽になるよ。音は何でも音楽になる。音を出そう」と歌いながら、それぞれの楽器を弾いたり、歩き回ったり、思い思いの姿を舞台の上で表しました。
「音楽の祭典」というコンサート企画では、この「音は、何でも音楽になる」というのがサブ・テーマでもありました。

「おすすめグッズ」

公演での演奏はEKOグルッペンがほとんどの曲を演奏しましたが、バンドとしての独自の曲の他にも、音楽のセッションで使われる曲もいくつか演奏しました。
しかし、セッションのように僕が中心となる形ではなく、グループの演奏に合わせて他の出演者がそれぞれの楽器を弾いたり、あるいは重度の障害を持つ出演者はサポートの人と一緒に音楽を楽しむ、という形で行われました。
また、EKOグルッペンのオリジナル曲の演奏では、出演者がコンサートの観客の役もしました。
総体的にこの公演は、舞台の上でデイセンター利用者と職員を分けることをせず、またEKOグルッペンも舞台を構成しているものの一つであり、観客もただ観たり聞いたりするだけでなく全員が参加するようにして、舞台と観客が一体になるように創られていました。
そこでは、デイセンター利用者ということや、障害を持つ持たないにかかわらずに、そこにいる全員がそれぞれ共感することを可能にしてくれる音楽への賛美の気持ちが込められていて、そこに集まったすべての人がそれぞれの垣根を越えて、純粋に音楽を楽しむという場でもあったのです。
会場全体が手をつなぎ、セッションでも使う「終わりの曲」を歌ってフィナーレが終わると、会場から舞台へ上がる人が続々と出てきて、しばらくの間舞台は人で埋まってしまいました。
感涙を浮かべる人、喜んではしゃぎ回っている人、家族や知人に囲まれて賞賛の言葉を心地良さそうに聞いている人、どうしてか分からずにただウロウロしている人など、目の前の様子を見て、僕もようやく公演が成功に終わったのだと思う余裕も出てきました。
こうして、スウェーデンで最初の、デイセンターの総勢75名による公演が終わりました。
⚫︎市内公演へ
コンサートホールでの公演は、結果的に大成功を収めました。
この公演はマスコミでも報道され、それ以来EKOが演奏する場も広がっていきました。
特に、障害者ケアを担当する県自治体の援護局からは、職員募集と障害者ケアの広報を兼ねたキャンペーンにEKOの出演を依頼され、年間20回も市内の小・中学校で演奏することになりました。
学校の生徒にしてみれば、今まで知的障害者がステージに立ってロックを演奏するなど見たこともなかったので、会場となった体育館では演奏が始まる前までは興味津々だったのが、いざ演奏が始まると、椅子の上に立ち上がったり舞台の前で踊り出したり、まるで本物のロックコンサートのようになりました。
演奏が終わると大勢が舞台に駆け寄り、メンバーたちにサインを求めたほどです。
リーダーの方には誰もサインを求めてはこなかったので、県の援護局の思惑はきっと当たって、目的を達成したのであろう、とリーダーたちも納得したものでした。

「おすすめグッズ」
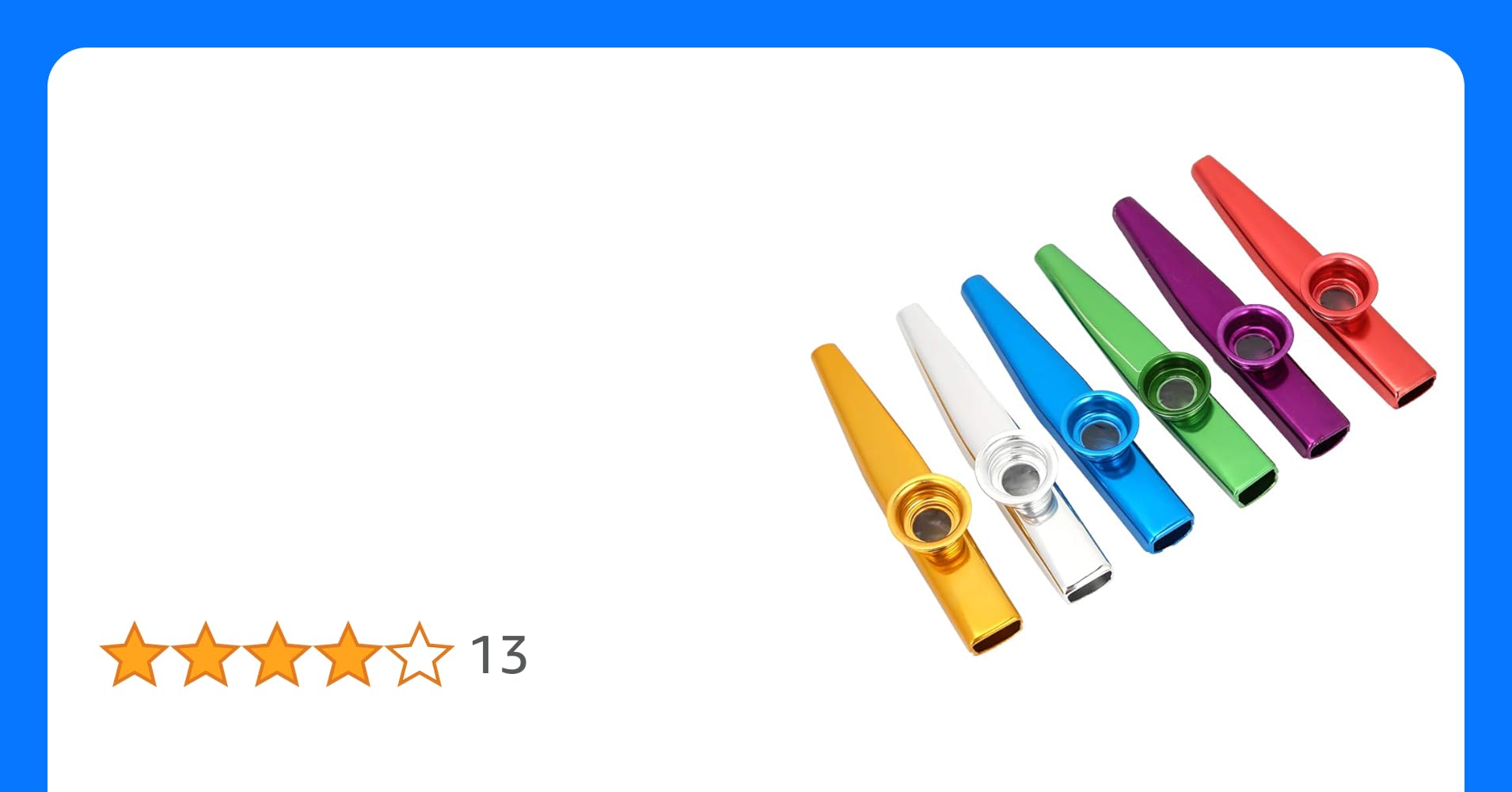
この他にも、学習連盟や労働組合、教会や余暇活動の青少年センターなどからも公演を依頼され、演奏の場も大きな舞台へと広がっていく中で、バンドのメンバーひとりひとりもそれぞれ経験を積んでいきました。
デイセンター回りで始まった演奏の場は、こうしてコンサートホールでの公演をきっかけに、障害者ケアの外に向けて、ストックホルム市内全域に広がっていきました。
⚫︎オン・ザ・ロード
市内公演が増えると、もちろん他の地方にも行ってみたくなります。
大型バスを借り切っての公演ツアーは、バンドのステイタスも上がるというわけで、国内公演にも出かけるようになりました。
いつも演奏の時はみんな一緒なわけですが、ツアーでは何日も一緒に行動しなければなりません。
サポートの体制もメンバーのニーズに合わせて決めたり、必要な役割などもいろいろ分担しなければなりませんが、普段から作業や演奏の場でそれぞれの役割はある程度決まっていたので、問題はありませんでした。
ツアーともなると、演奏のことや器材の運搬や仕込みだけでなく、食事や洗濯などの必要も出てきます。
それらは、お母さん役のビルギッタとギュードルンドが引き受けました。
地方によってはホテルに宿泊もしますが、時には市営キャンプ場のバンガローに泊まることもあるし、スポーツ施設に宿泊することもあります。
洗濯となると、何せ二十人もの大人数では洗濯機の確保が難しいこともあります。
それで、ツアーの日程を見ながら、ホテルに泊まる時など、ビルギッタとギュードルンドは風呂のタブをお湯でいっぱいにして、二十人分の洗濯をしました。
舞台では、激しい動きのために全員汗だくになります。
汗を掻く程、その日の演奏に力が入った証とも言えます。
そんな時には、ビルギッタもギュードルンドも洗濯で汗まみれになるのですが、ツアー中は、そんなわけでEKOのビールの消費量も確実に増大しました。

「おすすめグッズ」
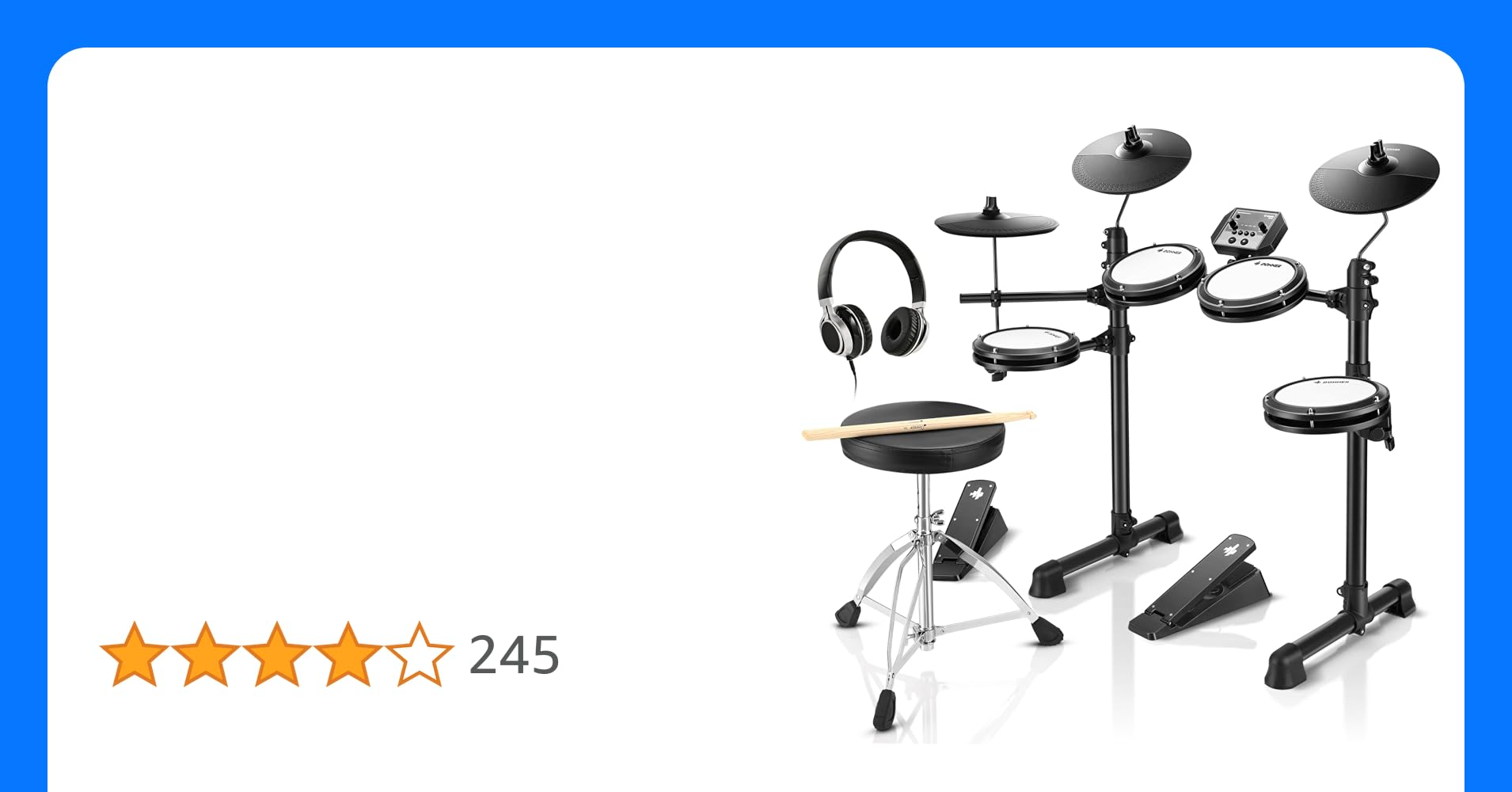
スウェーデンの中部地方ダーラナを越えて北に向かうと、途端に距離感覚がおかしくなります。
隣の町まで、ストックホルムの感じだとせいぜい何キロといったものが、ダーラナ地方では何十キロにもなり、もっと北へ行くと、それが何百キロ単位になるのです。
なので、この地方に住む若者などがディスコにでも行こうとすると、場合よっては200キロも離れた街に行くことも珍しくないそうです。
とにかく町と町の間に大森林があるのですが、感じからすれば、果てしない大森林や大原野の中に、ポツンポツンと町や集落があると言った方がわかりやすいかもしれません。
何時間もそんな大原野をバスに揺られていると、眠くなれば眠りますが、そうでもない時にはみんなで歌でも歌わなければ間が持てません。
だからというわけでもないですが、とにかくバス旅行には歌がつきものです。
また、そんなひと時が、グループの仲間意識をより強いものにしていきました。
もちろん、いつも快適なわけではなく、しばらくストックホルムを離れていることで寂しくなったり、環境がコロコロ変わるので、その変化のテンポに合わせることに疲れてくる者もでてきます。
そんな時には、やはりサポート職員であるアニカが、メンバーの精神的なサポートをする役目を担いました。
みんなの話を聞いてやったり、時には元気づけるように励ましたり、別にアニカがその担当と決まっていたわけではないですが、そういう役というのは、長い間一緒にいると自然に決まってくるものです。

旅をしていると、いろいろなエピソードも生まれます。
ある夏の頃、ダーラナ地方にツアーに行った時のことですが、ダーラナ地方はスウエーデンでも有数の観光地でもあるので、キャンプ場のバンガローに泊まることになりました。
サポート体制は今まで通り、それぞれ気の合う者が組むということで、ニッセのサポートはベース担当のペーテルというリーダーがすることになりました。
僕は彼らの隣のバンガローに泊まったのですが、夜中になるとペーテルが「ニッセ、うるさくて寝られないぞ!」という声がしばしば聞こえるので、何回も目を覚ましてしまいました。
ところが、明け方近くに、今までない大声でペーテルが「何やったんだ、ニッセ!」と怒鳴る声がしたので、何事かと、彼らのバンガローに行きました。
見ると、ペーテルは自分の靴を手に持ちながら、また大声で「ニッセ、何やったんだ!」と怒鳴っていました。
僕も、ニッセが何かやったのかと思ってニッセのベッドを見ると、空っぽです。
小さな小屋なのでベッドにいないとすれば、外しかありません。
何があったのかと少し心配になりながら外に出てみると、僕のバンガローの反対側で、ニッセが素っ裸で腰をかがめ、笑いを殺そうとしながらも止まらないとでもいうように、口に手を当てて笑っているのが見えました。
戻ってペーテルにわけを聞くと、ペーテルが夜中にトイレに行こうと思って靴を履くと、中がびしょ濡れになっていたそうです。
ペーテルはニッセのいびきが凄くて眠れなかったそうで、起きた時は寝ぼけ目でした。
なので、靴の中身が何であったのか咄嗟に分かるほど頭がスッキリしていなかったらしいのですが、次第に目が覚めて、それが普通の水ではないことに気がついたらしい。
ペーテルはニッセのいびきで眠れず、ニッセは眠っているとペーテルに「うるさい!」と言われて、これまた起こされる。
寝不足で、ニッセがトイレに行くつもりで寝ぼけていたのか、あるいは、ペーテルに怒鳴られて眠れなかったことへの仕返しなのか、ニッセはその後もその真相を明らかにしていません。
「おすすめグッズ」

![]()



