⚫︎「ネクスト・ストップ・モスクワ」への参加
1989年といえば、ロシアがまだソ連と呼ばれていた終わりの頃で、ゴルバチョフの「ペレストロイカ」旋風が起きていた頃です。
この頃は、旧ソ連の内部で表現の自由を求めていろいろな動きがありましたが、スカンジナビアの若者の間で、これら旧ソ連の若者たちと自由に交流しようと言う運動が起きました。
若者たちはその中で「ネクスト・ストップ・モスクワ」というイベントを立ち上げ、デンマーク、スウェーデン、ノルウェーのスカンジナビア諸国から5000人の若者がモスクワに行き、現地の若者たちと文化交流を行おうというものでした。
「ネクスト・ストップ・モスクワ」というのは、バスなどでいう「次の停車は、モスクワです」という意味です。
つまり、スカンジナビアの若者たちが、バスに乗る感覚でモスクワに集まり交流し、そしてモスクワの次の停留場は、また改めて決めようという企画でした。
その若者たちの中に、エクトルプ・デイセンターの職員をしていたカメラマン志望の女性がいて、ある日、EKOもそのイベントに参加できないだろうかと話を持ちかけてきたのです。
「ソ連では、まだ市民が自由にものを表現する機会が少ない。そこで知的障害者のグループであるEKOがモスクワに行って、大勢のモスクワ市民に、障害者が生き生きとステージで演奏する姿を見せてやりたい」というわけです。
もちろん、僕らもその話に飛びつきました。
モスクワに行って、障害を持つメンバーが自由にロックを演奏するというのも、正に「ロックン・ロール」じゃないですか…。

「おすすめグッズ」
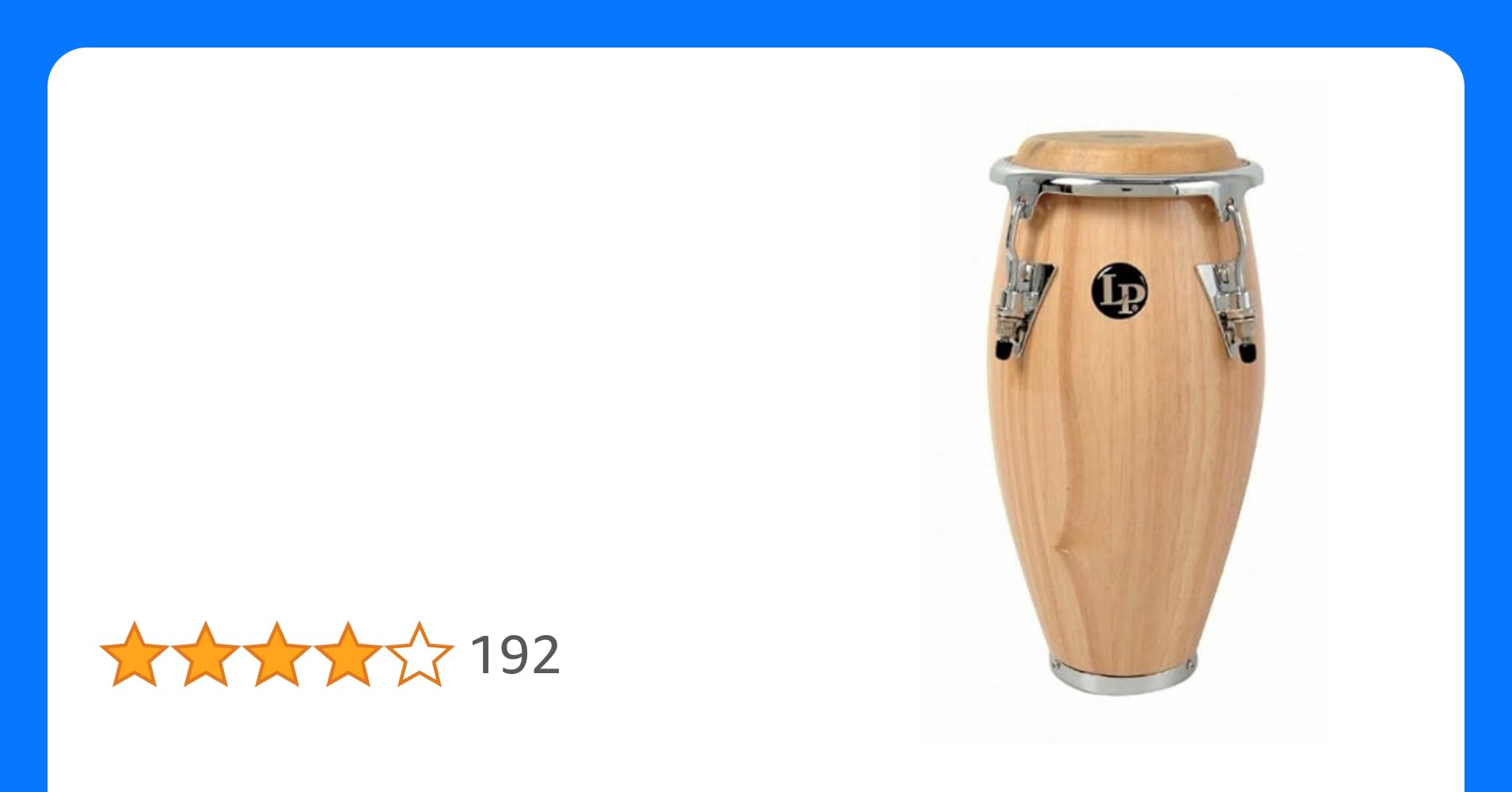
旅費や滞在費は助成金で補うということで、まあいろいろな苦労はしましたが、社会省に頼み込んだり、とにかく考えられるすべての手段を駆使して、とにかく参加のメドがつきました。
助成金を集める過程で、このプロジェクトを記録するという話になり、テレビチームも同行して密着取材もすることになりました。
そして、また大型バスを借り切って出発したのです。
受け入れ側では、宿泊するホテルのレストランでの演奏も予定していました。
それで、着いてから二日目、僕らは結構格調高い、ある大きなホテルのレストランのダンス場に機材を持ち込み、ろくに音響チェックもせずに、いきなり演奏を始めました。
僕らの演奏の前には、ロシアの楽団がポピュラー音楽やロシア民謡などを演奏していましたが、僕らが機材を持ち込んで仕込みをしている間中、何が起こるのかというような表情で興味深げに観察をしていました。
お客も、おそらく障害者というのは今まで見たことがないというような表情で、これも興味深げに見たり、あるいは見ない振りをしていました。
そして演奏が始まると、ロシアの楽団もレストランのお客も最初の二曲くらいは目を丸くして見ていましたが、次第に口元に微笑みが浮かんできて、曲が進むにつれて手拍子をするようになり、演奏の中頃にはダンスフロアに出てきてダンスを始めたのです。
ダンスにも次第に熱が入り、みんな汗を流して踊っていました。
演奏が終わると、「アンコール」の声が鳴り止みませんでした。
ロシアの楽団のギター弾きは、僕らのギターを珍しそうに触り、僕が使っていたピックをプレゼントすると、嬉しそうに、何回も「スパシーボ(有難う)」を繰り返しました。
次の公演は市内の養護学校ということでしたが、行ってみると、一般的に僕らが知っている養護学校というのとは、まったく様子が違っていました。
そこは寄宿舎のある学校で、寄宿舎の建物には50人くらいの生徒が二列に並んで寝るように、ベッドがきれいに整頓されていました。
演奏が予定されていた体育館のような場所で演奏が始まる頃には、200人くらいの生徒がすでに集まっていました。
しかし、どこを見ても、僕らが普段接している知的障害をもつ子供の姿は見えなかったのです。
中には肢体不自由児という生徒もいましたが、ほとんどの生徒は、一見する限りでは何の機能障害を持っているのか、見分けがつかないのです。
もしかすると、親のない子どもであったり、あるいは何かの学習障害という児童たちかもしれないと思いました。

「おすすめグッズ」
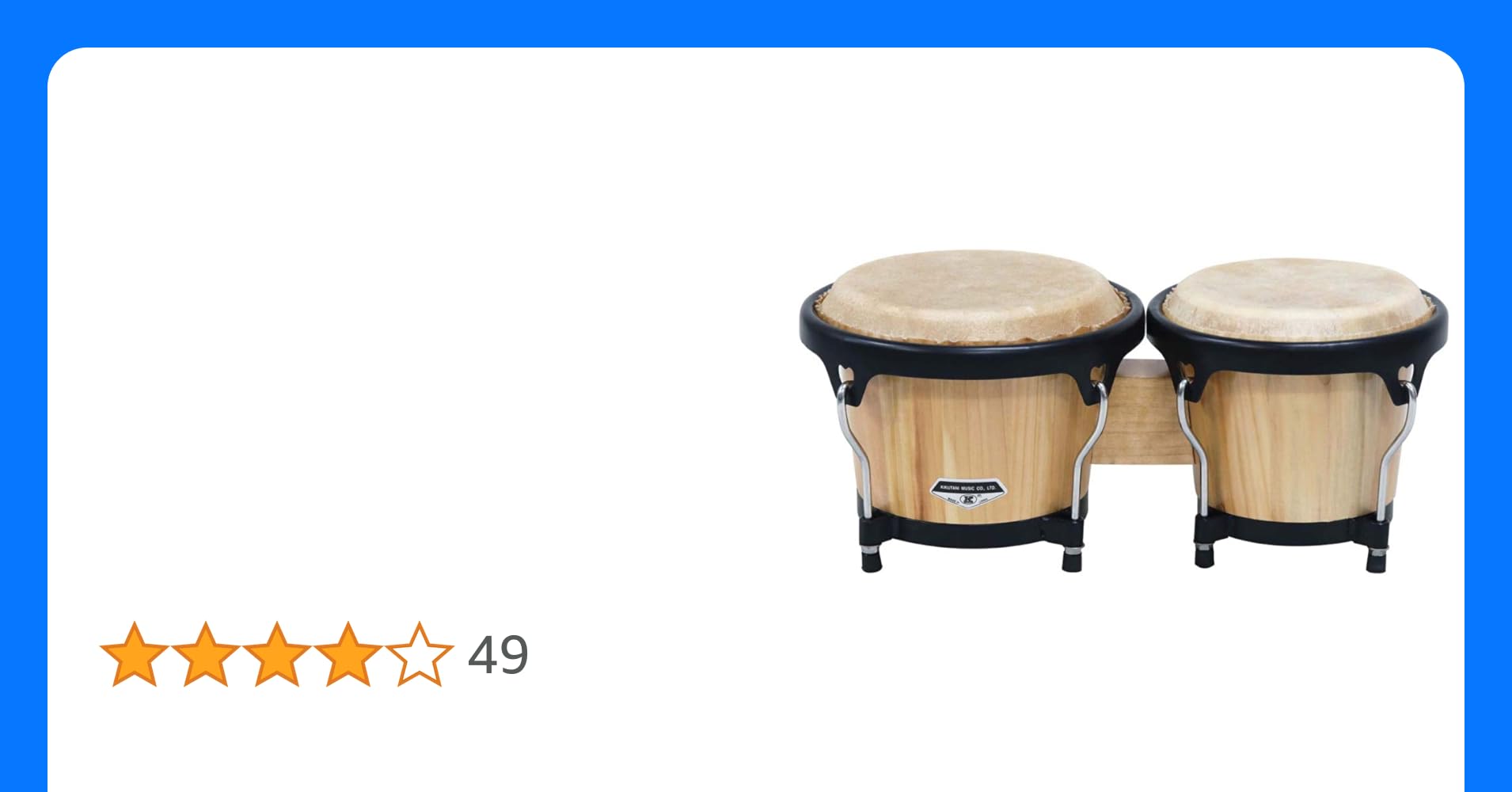
演奏中、それらの生徒は実に行儀よく席に座って、曲に合わせて手拍子を打ち、曲が終わるときちんと拍手もしました。
でも、スウェーデンの学校で見られるような素直な反応は、最後まで見られませんでした。
それにしても、養護学校というのに、ダウン症や自閉症の子どもたちはどこにいるのだろうと、僕らはそこから出てから話したものです。
宿泊ホテルから少し離れた公園を散歩している時でしたが、メンバーと歩いていると、近くを散歩していた若者が数人こちらを見ながら、小声で何かを話していました。
もちろんロシア語だから何を話していたのかは分かりませんが「Idiot(白痴)」という言葉は、僕にも聞き取れました。
⚫︎エストニアの視覚障害オーケストラ
モスクワでの公演の様子は、ソ連の放送局でも全国にラジオ放送したらしいです。
それと、僕らの受け入れ先だった団体が、当時はソ連に属していたエストニアの文化省に話をしたということで、それから一年後の1990年10月、僕らはエストニアの文化省と放送局から招聘され、全国公演を行いました。
エストニアの首都タリンまでは船で行き、タリン市の高級ホテルに宿泊して、1週間の間、タリン市やいくつかの地方都市を回りました。
エストニアは、言語的にはフィンランド語と同じ系の言葉を話し、また歴史的にもスウェーデンとは関係の深い国です。
モスクワとはまた違った雰囲気で、市民もどちらかというと物静かな感じがしました。
公演は、学校や地方の公民館など公共の施設で行われましたが、地域によって受け入れ方も様々でした。
ある地域では、その地域の障害者団体が受け入れ先で、そこの委員長はその後いくつかの公演にも同行しました。
彼も、また他の障害者団体も、僕らの公演を非常な熱意で迎えてくれて、地域にある障害者が作った工芸品などを展示してある場所にも案内してくれました。

この場合の障害者とは、身体障害をもつ人です。
彼らの話によると、このような演奏会に出かけるということ自体が全く珍しいことで、例えば障害者の団体で集まりがあったとしても、連絡することすら難しいというのです。
話をもっと聞いてみると、電話を持っていない人が多いというのです。
また、仮に近くに電話を持っている人がいて連絡がついたとしても、車椅子で出かけるのは難しいということでした。
タクシーというのもあるにはありますが、とても余暇に何処かへ出かけるためにタクシーを使う余裕はないと言っていました。
電話がないから連絡もつかないので、こうして集まるのも大変なんだ、という言葉に僕は凄く重みを感じて、その委員長が演奏会に何回も参加してくれる度に胸が詰まってしまいました。
知的障害者の施設も訪問しました。
スウェーデンにはもうなくなって久しいタイプの施設で、入所の施設と日中活動をする場がありましたが、日中活動の場はいろいろな訓練の場でした。
ある演奏会では、そこに住む障害児も招待され、演奏が始まると、見学で見た様子とはガラッと変わった喜びの表情を見せていました。
「おすすめグッズ」
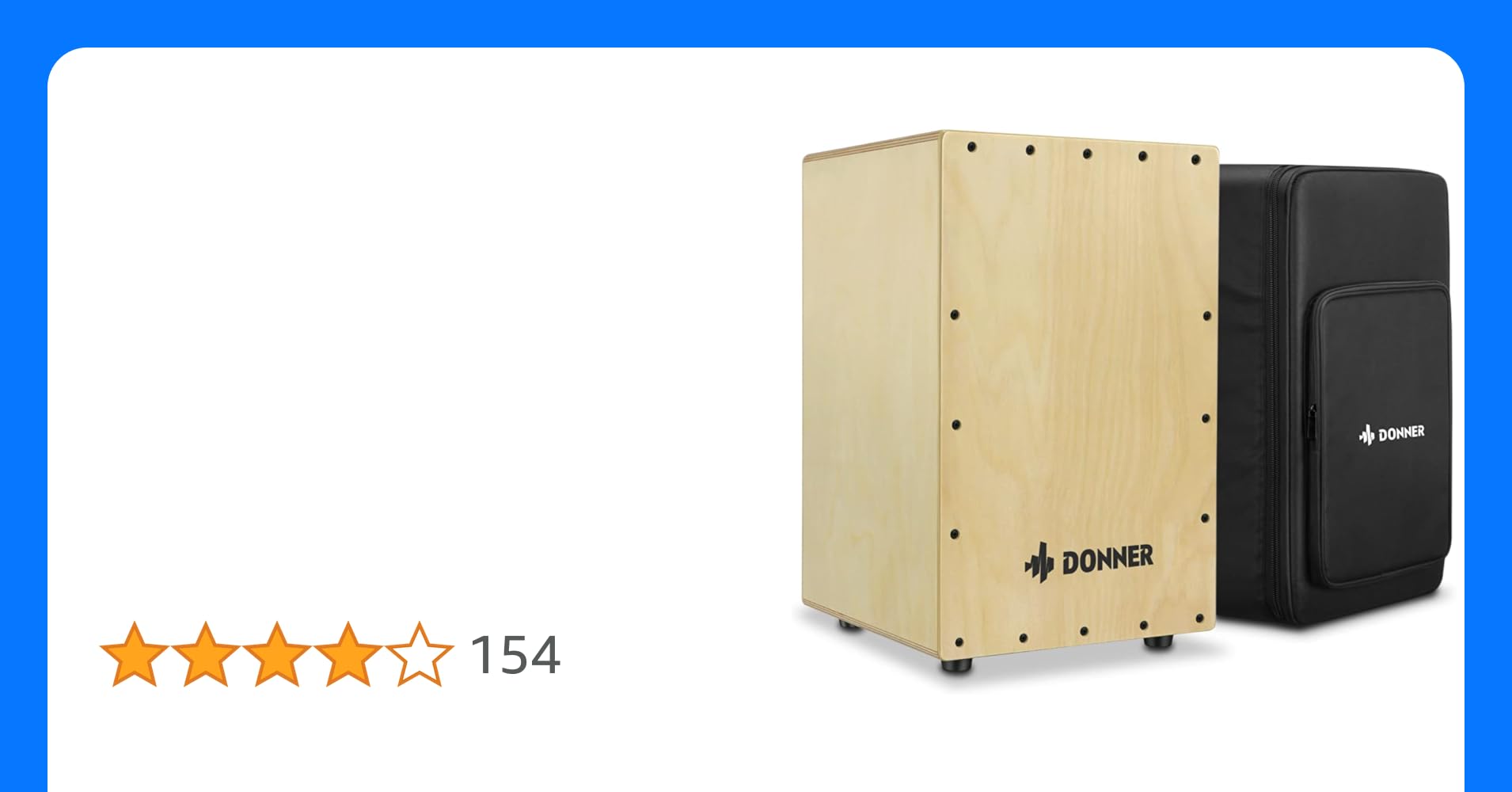
音楽というものにはもちろん接しているのでしょうが、もしかしたら喜びを表現するということとは違う接し方なのかなとも思いました。
同行していた英語を話す音楽の教師が、「うちの障害児があんな表情をするのは、初めて見た」と言うのです。
そういえば、ソ連の障害者教育理論というものが、世界的にも評価が高いということを思い出しました。

タリン市内で、ある視覚障害者のオーケストラと合同の演奏会をした時のことです。
演奏の場所は福祉関係のセンター風の建物で、その中にある大きな会場で演奏することになり、僕らは用意された機材や楽器の仕込みをして演奏を始めました。
視覚障害者楽団のメンバーは壁際に用意された椅子に座って、僕らのロック演奏をジーっと聞いていました。
手拍子もなかったし、曲が終わってからも別に拍手をするわけでもありません。
視覚に障害があるためか、ある人は耳を傾けるように、またある人は俯いたまま、何かを探るように黙って聞いていました。
やがて彼らの番になり、演奏者は係の人が準備したそれぞれの席につきました。
各々自分なりの格好をして、そのまま何かを待っている様子でした。
やがて、軍服かと思われるようないかつい格好をして帽子までかぶった男性が前に出てきて、指揮棒を鳴らすと演奏が始まりました。
一般的な交響楽団のような編成で、曲も交響曲やロシア民謡などでしたが、演奏の途中でふと気がついたのですが…
交響楽団に指揮者がいるのは何も不思議ではないのですが、楽団全員視覚障害者です。
みんなそれぞれの姿勢で音を聞きながら演奏しているのですが、誰も指揮者の指揮棒を見ていないのです。
演奏は確かなもので、僕らも久しぶりに交響楽団の演奏を聞いたわけですが、演奏が終わると、指揮者は軍隊長の帽子を取り、タクトを小脇に挟んで礼儀正しくお辞儀をして、サッと下がっていきました。
残りの楽団員は、しばらく席に座ったままでしたが、指揮者が退場したのを察したのか、一人ずつ自分のテンポで舞台から下りていきました。
視覚障害者の交響楽団で、指揮者はどうやって指揮棒で演奏をまとめていったのか、一度聞いてみたいと思いました。
「おすすめグッズ」
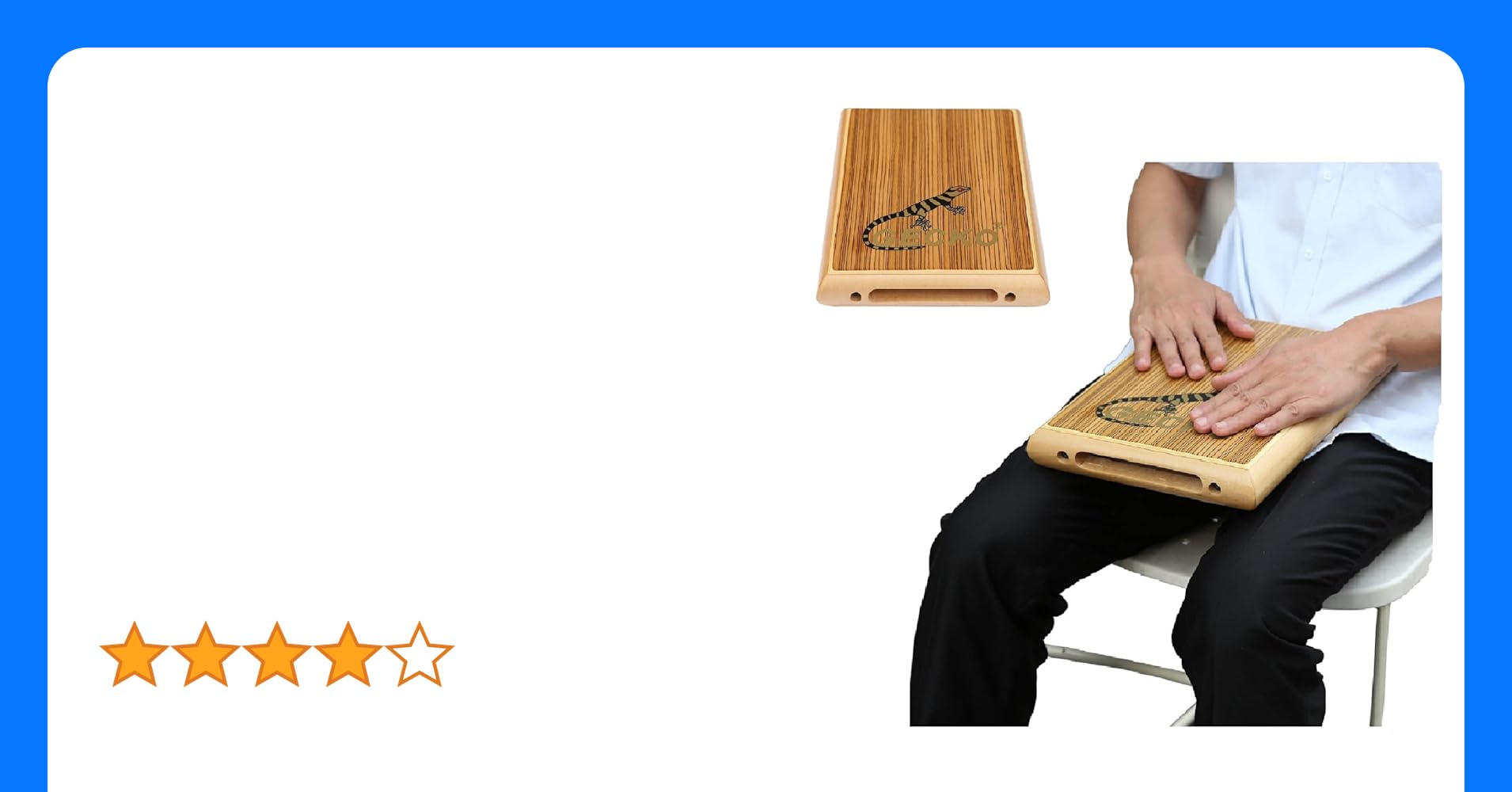
⚫︎トリニダード・トバゴの「スペシャル・チャイルド」
1991年にEKOがエクトルプ・デイセンターから独立して、独自の「EKOデイセンター」になり、新しい拠点に引っ越すと間もなく、ストックホルム市にある音楽博物館の館長から連絡がありました。
カリブ海にあるトリニダード・トバゴに公演に行けないかという問い合わせです。
その館長は、本人も軽い脳性麻痺の症状を持つ人ですが、カリブ海諸国の音楽、とりわけトリニダードのカリプソのリズムの権威です。
今まで何回となくトリニダードを訪問し、スティールパン(ドラム缶を利用した、トリニダード独特の楽器)のバンドをスウェーデンに招聘もしていました。
話によると、あちらの政府関係の奥さんが養護学校設立のためにチャリティコンサートを開くので、EKOを招聘したいと言っているということでした。
調べると、赤道直下に位置するトリニダードとトバゴという二つの島からなる国で、気候は年間を通して気温が30度ということで、北欧からみると常夏の国、白い浜辺に椰子の木、それにカーニバル…。
すぐに受託の返事をしました。

飛行機はストックホルム郊外のあるアルランダ空港から直行便が出ていますが、人数の関係で、グループを、直行便とロンドン経由、それにマイアミからバハマ経由という三つのグループに分けて、最終的にトリニダードで落ち合うことにしました。
僕のグループは直行便で到着しましたが、飛行場に着くとすぐ、VIPの待合室に通されました。
他のグループは次の日に到着するので、とりあえず、夜の暗闇の中、首都ポート・オブ・スペインの最高級ホテルに向かいました。
飛行場から市内までは迎えの車で行ったのですが、見ると沿道のいたるところに、家の屋根や庭の木、果ては芝生にまで灯りが燈っていました。
聞くと、その日はヒンズー教の祭日だということです。
この国の人全部がヒンズー教とも考えられないのでさらに聞くと、案内の人が、「この国は、みんなどこかの血を引いているから、何の宗教だってお祭りをするんだ」と言っていました。
昔、イギリス、スペイン、フランスなどの強国がほとんど同時にこの島に来て、アフリカやインドなどの植民地から人を連れてきたそうで、とにかくいろんな人種がいます。
出会う人の多くは、その圧倒的多数が黒人系ですが、アフリカ系、インド系、アラブ系、白人系、中国系と様々な人種が混血されているようで、そこでは自分が何系であるかなどということを考えることさえ無意味であるような気もしました。

「おすすめグッズ」
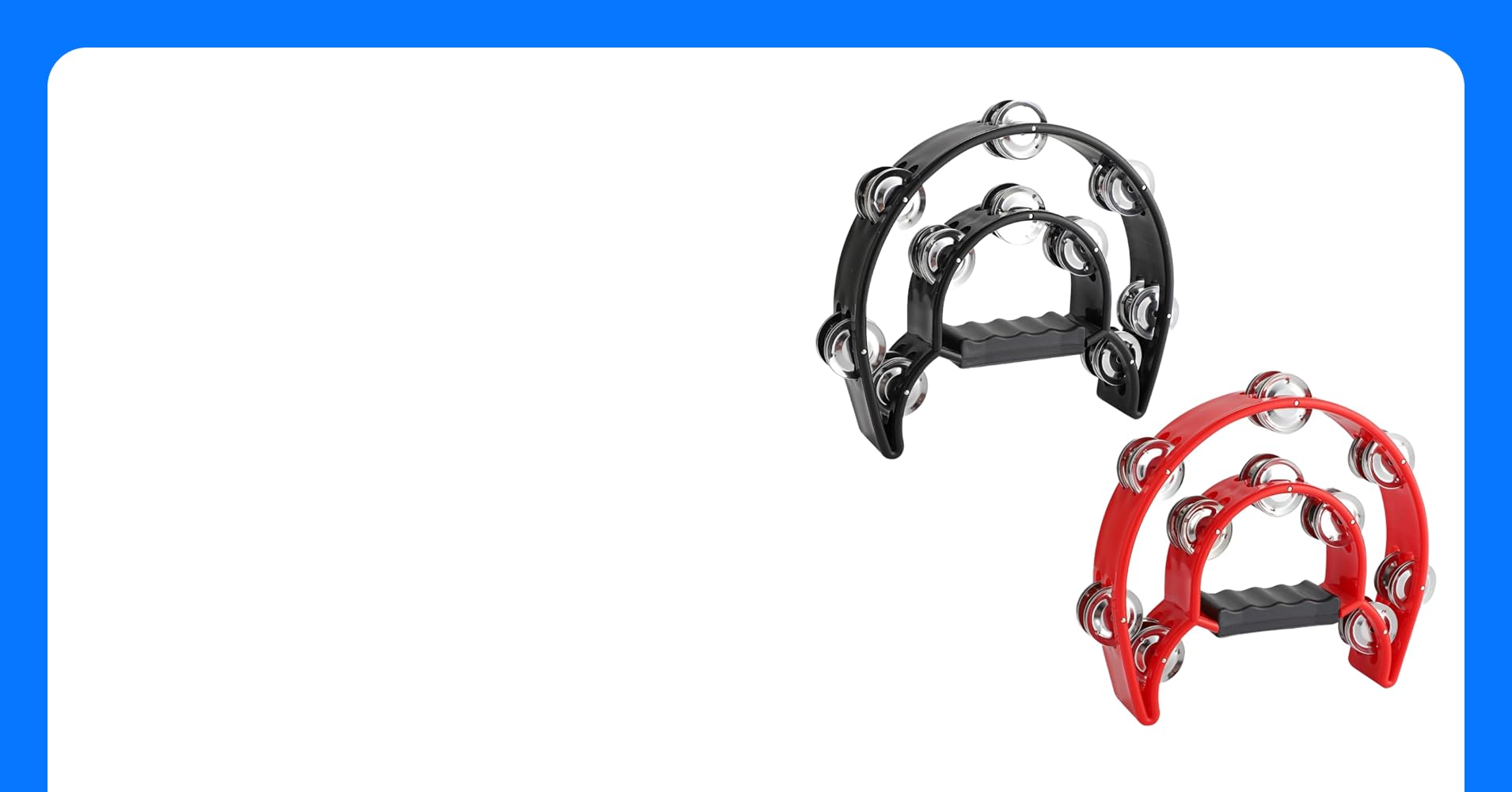
さて、僕たちを招聘したのは、元大臣の経歴を持つ白人系の野党党首の奥さんでした。
孫にダウン症の娘がいます。
国中にいろんな人種がいるので、他の人と違って見えるということでは特別人の目を引きません。
その孫娘も、近所の人からはとても可愛がられている印象を受けました。
しかし、ダウン症ともなればそれに適した学校が必要ですが、いわゆる養護学校というものは数が少なかったのです。
そのため、チャリティショーを開いて資金を集め、新しい養護学校を開くというのが今回のイベントの趣旨でした。
ちなみに、養護学校のことを、その奥さんは「スペシャル・チャイルド・スクール」と呼んでいました。
知的障害でも障害児でもない、”A Special Child” です。
公演会場は、8000人を収容する市立競技場でした。
僕らも、今までいろんなところで演奏しましたが、8000人というのは、想像を超える数字でした。
実際には、その競技場の中央にステージがあり、競技場の観客席の半分を使うということで当日は3500人集まったということですが、とにかく大きなコンサートであったことには変わりありません。
おまけに、EKOの他にもトリニダードを代表するポップバンドや、高校のスティールパン演奏全国大会で優勝したグループなども競演するということで、前評判も非常に高いものでした。

「おすすめグッズ」
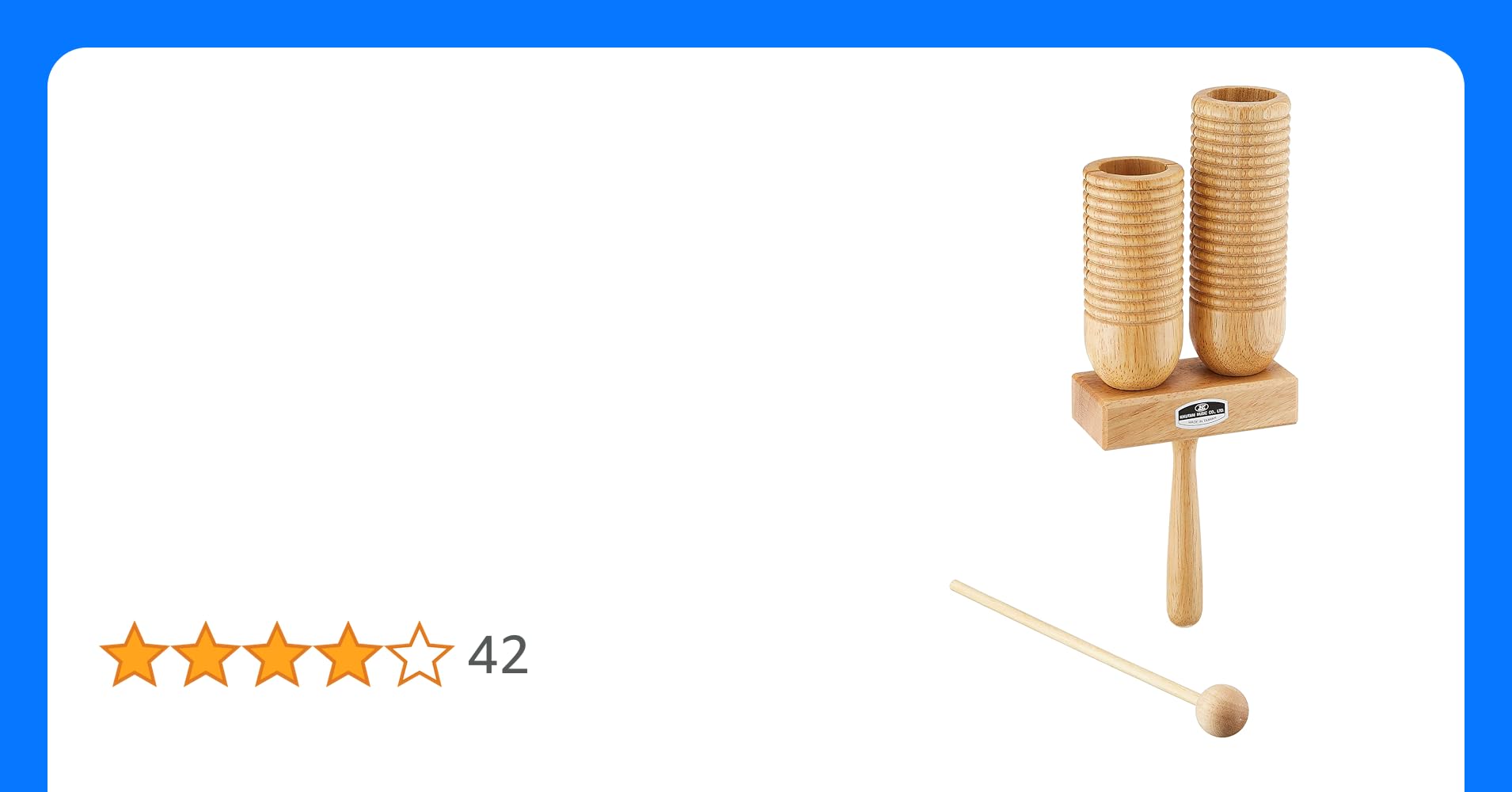
開演の時刻が近づくと、会場はほとんど満席の状態になり、カーニバルの衣装を着た集団もあちこちにいました。
トリニダードは、ブラジルと並んで年に一度のカーニバルがあるので有名で、僕らが滞在中は、スティールパン・バンドの練習の音が、町中どこからでも聞こえてきたものです。
大きな野外ステージの前には、貴賓席が用意されていました。
何と、政治家や偉い人たちと一緒に、僕らのためにも用意されたものでした。
突然、スウェーデンの国家がテープで流され、参加者全員が起立すると、僕らが持っていったスウェーデン国旗が掲揚されました。
僕らも、もちろん起立して、スウェーデンの青地に黄色の十字架が美しい国旗を仰ぎ見ました。
「オリンピックやスポーツの世界選手権で表彰台に上る選手は、国旗掲揚、国家演奏をこんな気分で味わうんだろうか?」と、ふと思いました。
僕らのために、スウェーデンの国歌が流され国旗が掲揚されて、観客が敬意を評している…。
ふと隣を見ると、メンバーもスタッフも神妙な顔をして国旗を眺め、国歌を歌っていました。
「僕らのために…」またそう考えた時、目頭が熱くなりました。

3500人の観客を前にした野外ステージにスポットライトが当たると、ステージから見る観客席は真っ暗で、観客の反応も見えにくいものです。
でも、ちょうどその日はニッセの誕生日でもあったので、僕が音頭をとって「ハッピー・バースデイ」と即興で歌い出すと、3500人の大合唱が後に続きました。
それで、観客席にも僕らのメッセージが届いているのだと確信できました。
トリニダード滞在中は、政府観光局から特別の案内人が差し向けられていて、公演前には島中を案内してくれていました。
公演が終わってホテルについてきたその案内人は、「正直言って、初めのうちは、一体このグループに何ができるのかと思っていたけど、あの公演を見て、みんなプロだということが分かった。今度プライベートでくることがあったら、いつでも連絡してほしい」と言って、改めて握手を求めてきました。
公演が成功だった証を、ここで貰ったと思いました。
「おすすめグッズ」
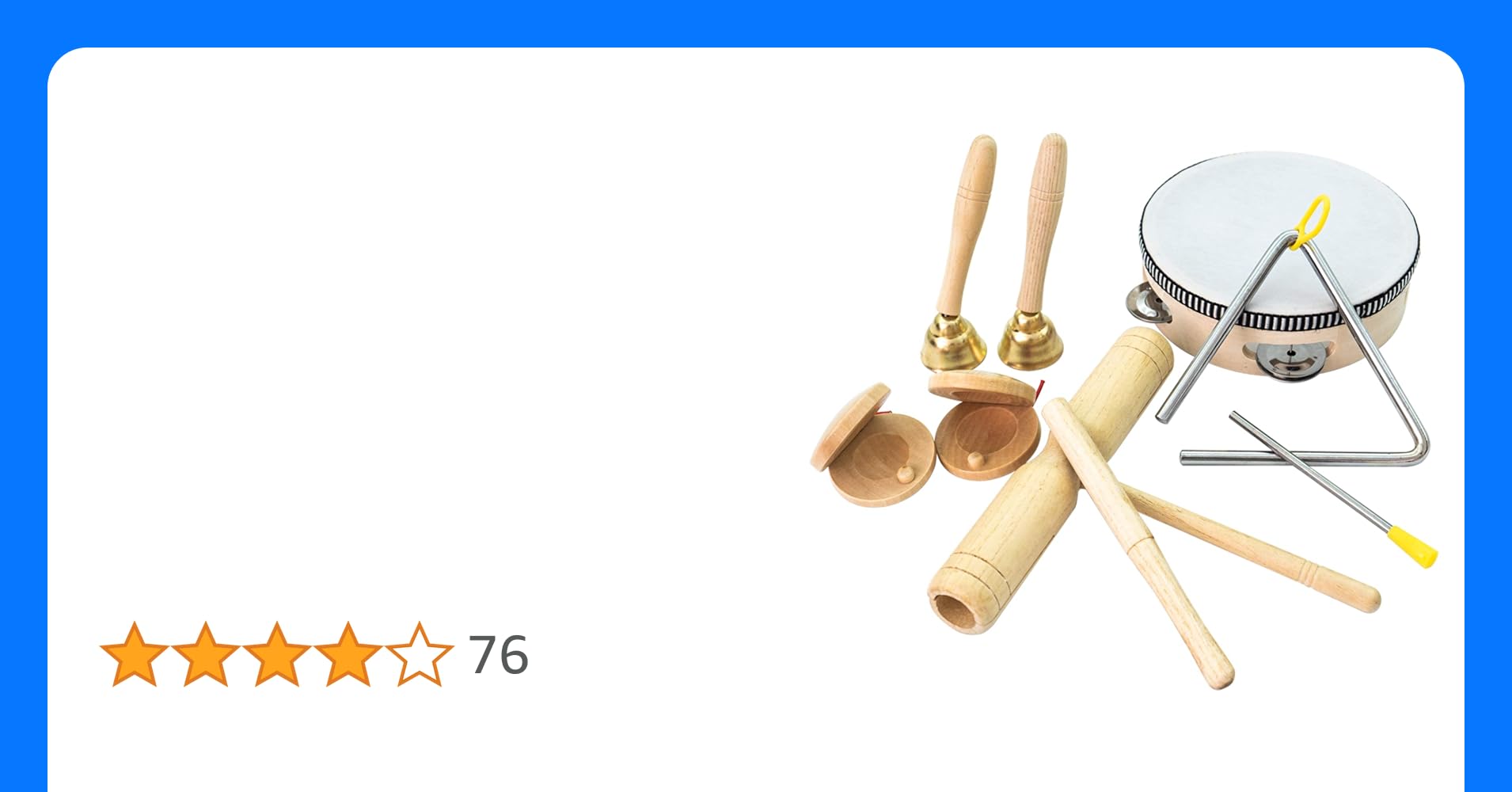
![]()



